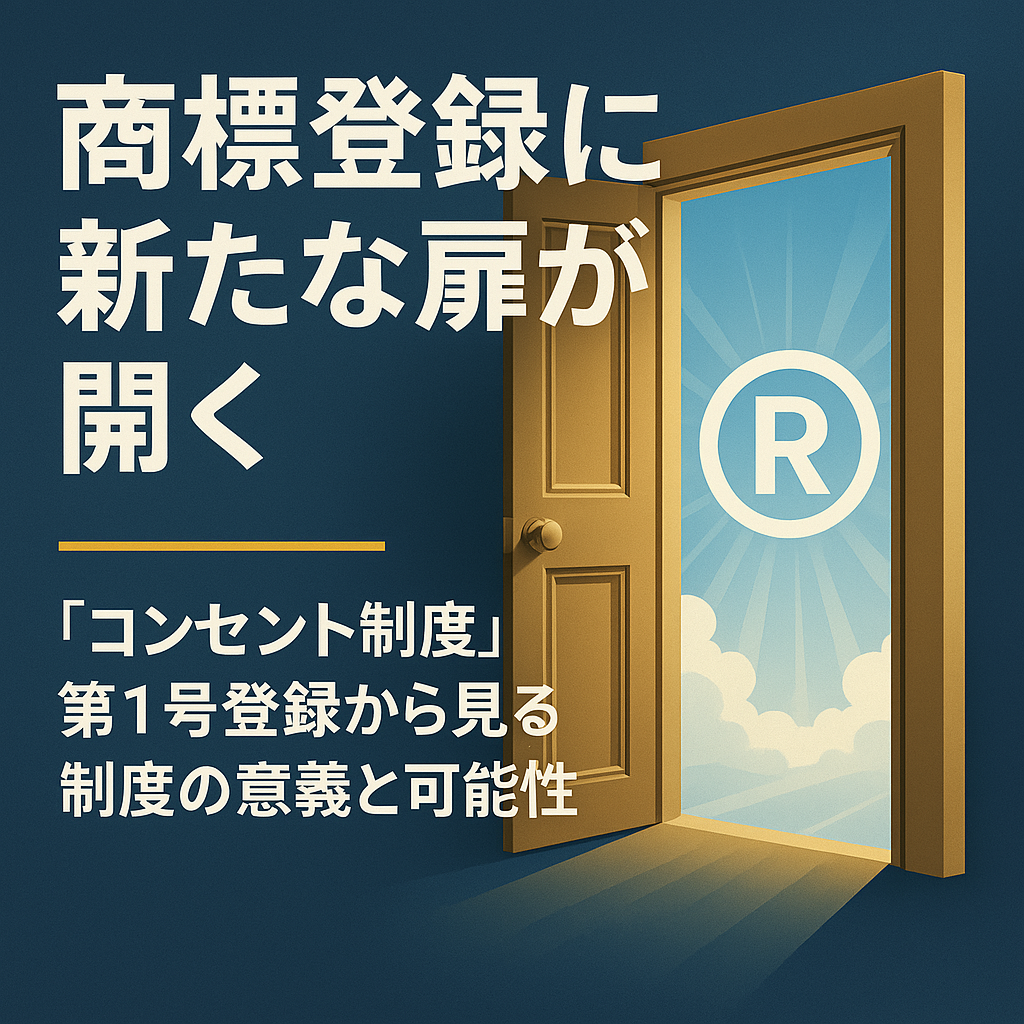2025年4月7日、特許庁は商標法改正に基づく「コンセント制度」による初の商標登録を認めたと発表しました。この新制度は、既存の商標権者の“承諾”と“混同の恐れがない”という条件を満たせば、同一または類似の商標でも登録が可能となる画期的な仕組みです。今回は、酒造メーカーの車多酒造による「玻璃(はり)」という商標がその第1号として認定されました。
制度の背景:「コンセント制度」とは何か?
従来の日本の商標制度では、たとえ事業分野や商品に差異があっても、既存商標と類似する新たな商標の登録は基本的に認められませんでした。これは“混同防止”という商標制度の根幹に基づくものであり、一見すると消費者保護に適った運用です。
しかし、その一方で、スタートアップや中小企業が新たにブランドを立ち上げようとする際、すでに使われている単語やイメージを避けざるを得ないという“ネーミングの壁”にぶつかることも少なくありませんでした。
これを打開する仕組みとして、2023年に商標法が改正され、2024年4月から「コンセント制度」が導入されたのです。
制度の核心:「承諾」と「混同の恐れなし」
コンセント制度のポイントは、次の2つの条件が揃うことです。
- 先行商標権者の明確な承諾があること
- 消費者に“出所の混同”が生じる恐れがないと特許庁が判断すること
つまり、当事者間での合意だけでなく、あくまで“消費者に誤解を与えないかどうか”という観点が審査の軸になります。
初の適用事例:「玻璃」に見る制度の意義
今回、第1号として登録が認められたのは、車多酒造が申請した「玻璃」という酒の商標です。ギフト事業で知られるシャディが同名の商標を先に登録していましたが、両者の事業内容の違いやターゲットの明確な区別により、混同の恐れがないと判断されたものと考えられます。
ここで注目すべきは、「企業間の円滑な合意形成」と「行政による客観的判断」が両立された点です。これは、単なる制度の緩和ではなく、より柔軟で実務的な商標戦略の支援を意図していることがわかります。
制度の今後と展望
特許庁はこの制度を通じて、企業のブランド戦略の多様化を支援し、知的財産の活用による新規事業創出を後押しする方針です。すでにEUや韓国、シンガポールなどでは類似制度が存在しており、今後の国際的な商標制度の調和にも寄与すると期待されています。
結び:ビジネスの自由度を高める「知財の合意文化」へ
「コンセント制度」は、単なる法改正にとどまらず、知的財産の運用に“対話”と“合意”の文化を持ち込む重要なステップです。今後、商標戦略を柔軟に展開したい企業や、共存共栄の道を模索するプレイヤーにとって、新たな選択肢となることは間違いありません。
商標は「権利の壁」から「合意の架け橋」へ――その第一歩が、今まさに踏み出されたのです。