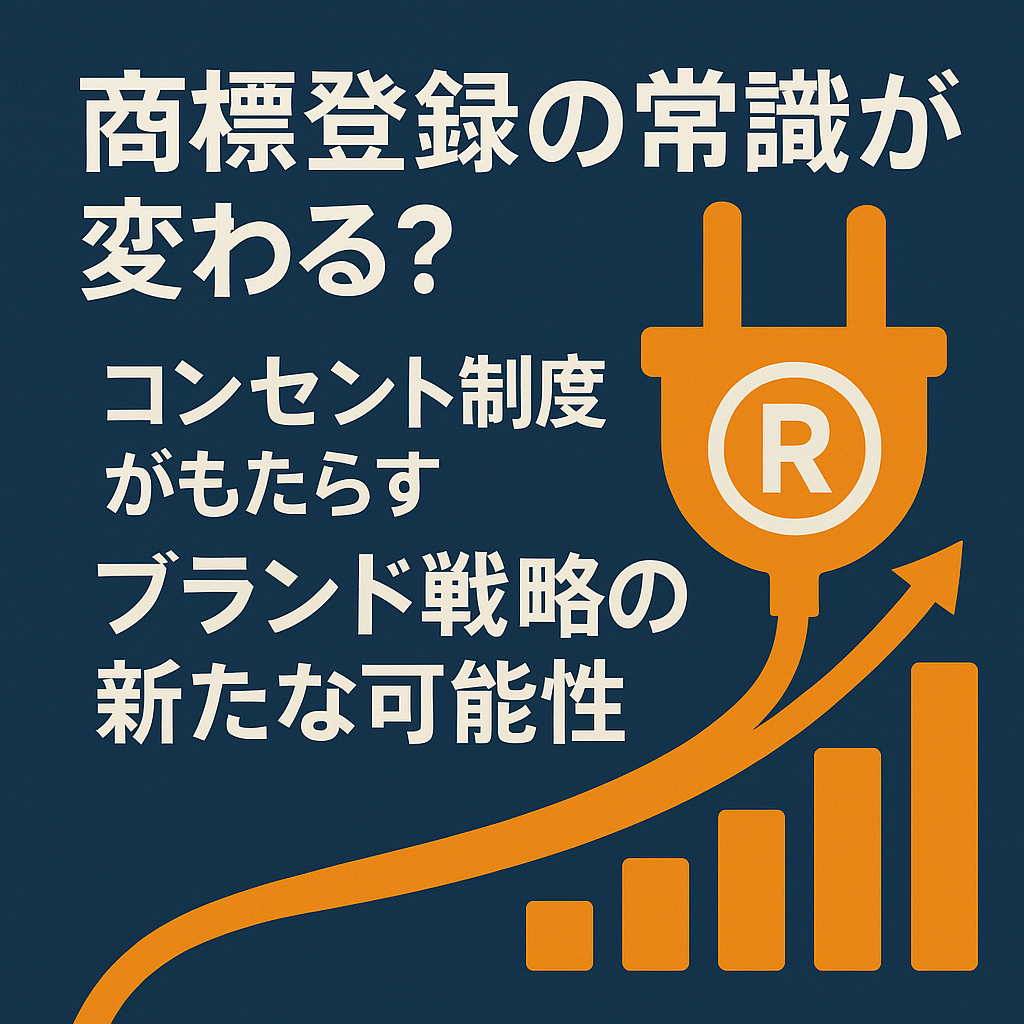はじめに
2025年4月7日、特許庁が「コンセント制度」を適用した初の商標登録を発表しました。
このニュースは、スタートアップや中小企業にとって、大きな意味を持つかもしれません。
「コンセント制度」とは、これまで商標登録ができなかったようなケースにも道を開く、画期的な制度です。
本記事では、この制度の概要と、実際に企業活動へ与える影響について考察してみたいと思います。
コンセント制度とは何か?
従来の商標法では、既に登録されている商標(先行登録商標)と同じか似ている商標は、原則として登録が認められませんでした。
これは、消費者がブランドを混同しないようにするためのルールです。
しかし、新たに導入された「コンセント制度」では、先行登録商標の権利者が「OKですよ(=コンセント)」と承諾し、さらに混同の恐れがないと認められれば、似た商標でも登録できるようになったのです。
なぜこの制度が注目されているのか?
特に注目したいのは、この制度が中小企業やスタートアップのブランド戦略を柔軟にする可能性です。
たとえば、せっかく魅力的な商品名やサービス名を思いついても、それに近い名前の商標が既に登録されていたため、泣く泣く別の名前に変える――そんな経験を持つ起業家は少なくないでしょう。
コンセント制度の登場によって、先行権者と良好な関係を築ければ、そのまま希望する名前での商標登録が可能になる道が開けました。
企業間の協調と共存の時代へ?
この制度がうまく機能すれば、「敵か味方か」という従来の排他的な商標戦略から、協調・共存型のブランド戦略へのシフトが進む可能性もあります。
もちろん、商標の世界は常にリスク管理と裏腹。安易なコンセントはブランド毀損のリスクにもつながるため、法的・ビジネス的な戦略眼が求められます。
国際調和の一環としての意義
実はこのコンセント制度、欧米をはじめとした多くの国ですでに導入済みです。
日本でもこれを採り入れたことで、国際的なビジネス環境との整合性が高まり、海外企業とのコラボレーションや進出もよりスムーズになると期待されます。
おわりに
商標制度の変化は、単なる法律改正にとどまりません。
それは「どうブランドを守るか」だけでなく、「どうブランドを育て、どう他者と共に使っていくか」という、新たな知財の姿勢を象徴しているように思えます。
今後、コンセント制度がどのように活用され、どんな判例や慣行が積み重ねられていくのか。ブランドを扱うすべての人にとって、注目すべきトピックです。