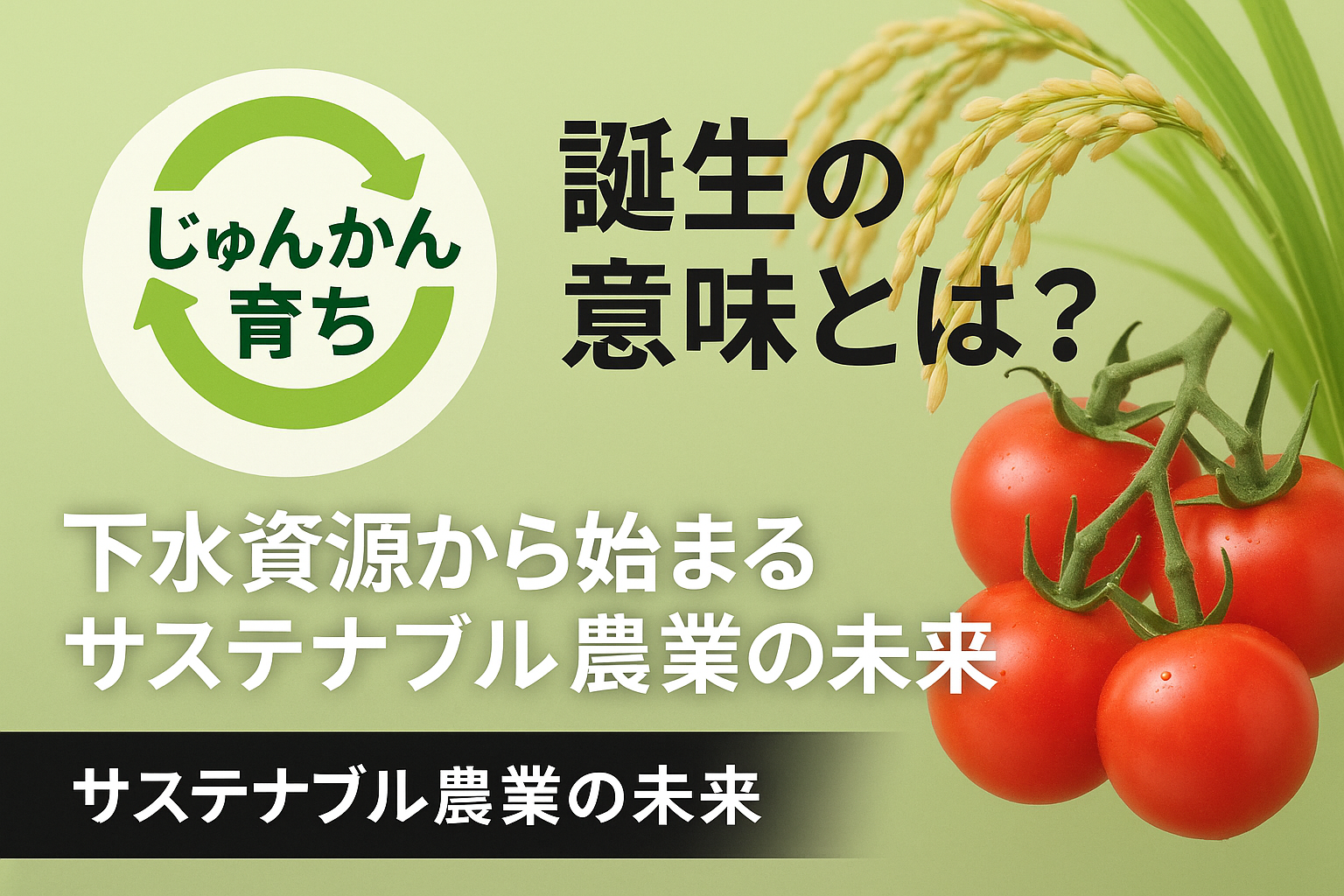見慣れぬ食材名の背後にある“じゅんかん”の思想
スーパーの青果売場に並ぶ「じゅんかん育ち」のトマトや米。名前は聞いたことがあっても、それが“下水道資源”を活用した農産物だと知ると、驚く人も少なくないかもしれません。日本下水道協会がこのたび「じゅんかん育ち」の商標を正式に登録した背景には、単なる名前以上の、環境と社会への深いメッセージが込められています。
下水道資源は「不快」から「資源」へ:社会の認識転換を狙う
これまで「下水」と聞くと、多くの人がネガティブな印象を持ちがちでした。しかし、再生水に含まれるミネラルや熱エネルギー、汚泥に含まれるリンや窒素といった資源は、農業にとっては極めて有用です。「じゅんかん育ち」は、これらを活用した農産物に新たな価値と印象を与える、イメージ戦略の一環といえるでしょう。
無償商標制度のインパクト:ブランドと普及の両立
今回の商標登録の最大の特徴は、「無償で利用可能」という点です。これはブランドイメージの統一と普及促進を同時に達成する巧妙な仕組みです。すでに使用していた生産者にもあらためて申請を求めることで、流通状況の把握やデータ収集にもつながります。国主導の取り組みとしては、透明性と効率性のバランスが取れた好例です。
“BISTRO下水道”の流れをくむ7年越しのブランディング
「じゅんかん育ち」は2017年の公募で生まれましたが、その前身は2013年から始まった「BISTRO下水道」戦略です。10年以上の取り組みが、ついに制度として結実した形です。農業とインフラという異分野の連携モデルは、地方自治体にとっても大きなヒントになるかもしれません。
最大の壁は「心理的抵抗」:突破の鍵は“透明性”と“物語性”
どれほど安全で美味しい食材であっても、「下水由来」と聞けば抵抗を感じる消費者は少なくないでしょう。ここで重要なのは、「循環型社会への貢献」という物語性の訴求です。さらに、製造プロセスの透明性や、食の安全に関する科学的根拠の提示が不可欠です。消費者教育とストーリーテリングが今後の鍵を握るでしょう。
循環の輪に私たちも参加できるか?
「じゅんかん育ち」は、単なる農産物ブランドではありません。それは、私たちの社会が環境負荷を減らし、持続可能な未来に向かうための象徴的な取り組みでもあります。食べることが資源循環への一歩になる時代、私たち消費者にも小さな選択の重みが問われています。