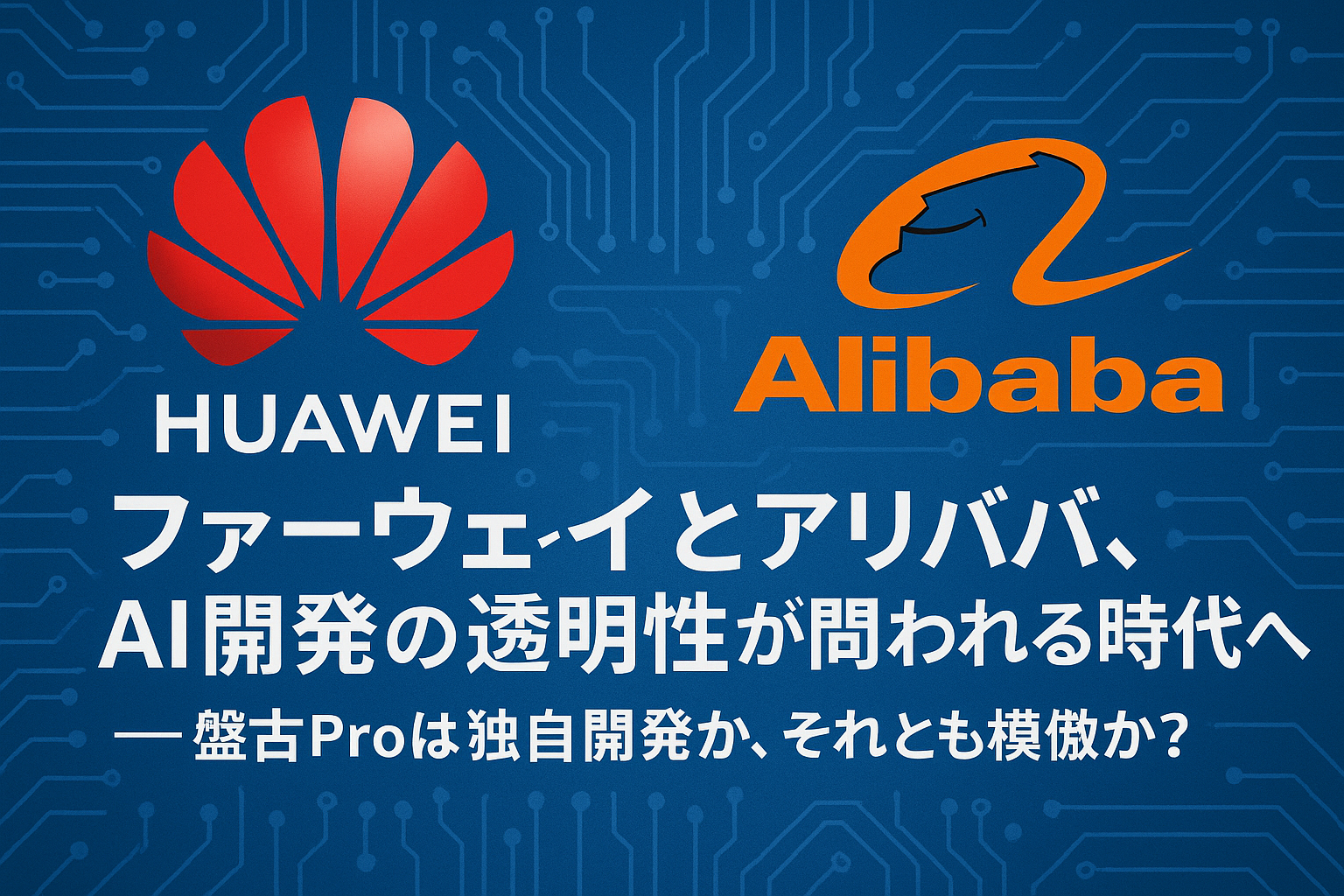──盤古Proは独自開発か、それとも模倣か?
2024年から続くAI開発競争において、中国企業も急速に存在感を増しています。そんな中、ファーウェイの大規模言語モデル「盤古Pro」が、アリババの「通義千問(Qwen)」を模倣した疑いが浮上し、再びAI分野における“信頼性”の問題が注目されています。
模倣疑惑とファーウェイの反論
問題の発端は、「オネストAGI」と名乗る団体がGitHub上で指摘した“異常な相関性”です。ファーウェイの「盤古Pro MoE」とアリババの「Qwen2.5-14B」の挙動や構造が極めて似ており、「アップサイクリングされた(既存モデルの再利用)可能性がある」として、著作権侵害や開発過程の信頼性に疑問を呈しました。
これに対し、ファーウェイのAI研究部門「ノアの方舟」は、「自社設計であり、Qwenベースではない」と真っ向から反論。さらに、自社製半導体「Ascend」上で動作する初の大規模言語モデルであり、オープンソースライセンスも厳格に遵守していると主張しました。
技術検証の“見えない壁”
ここで問題となるのが、「本当にゼロから開発されたのか」という点を客観的に証明するのが極めて難しいということです。AIモデルはブラックボックス的性質が強く、内部構造や出力結果が似ていても「偶然の一致」として片付けることもできてしまいます。
また、オープンソースが普及する現代では、他社コードを合法的に活用できる余地もあり、「模倣とインスパイアの境界」が曖昧になりがちです。これは中国だけの問題ではなく、世界中の開発者が直面している課題でもあります。
ファーウェイに突きつけられる“透明性”の壁
ファーウェイは2021年に盤古を初披露するなど、中国では比較的早期からAI開発に取り組んできました。しかし、その後のスピードはアリババやバイドゥにやや遅れをとっていたとも見られており、「盤古Pro」はその巻き返しを狙った存在でした。
今回の模倣疑惑が事実かどうかに関わらず、今後は単なる「性能競争」ではなく、「開発過程の透明性」が重視されるフェーズに入っていくでしょう。
特に政府の支援や独自ハードウェアによる“国産AI”を強調するファーウェイにとって、この透明性はブランド価値そのものを左右する可能性もあります。
AIの信頼は、技術力だけでなく「開発倫理」でも築かれる
AIの精度や性能も重要ですが、それ以上に今後は「どう開発されたのか」「どんなデータで学習したのか」といった“見えない部分”の信頼性が問われる時代です。
ファーウェイとアリババという中国の2大プレイヤーの動向は、国内だけでなく世界のAIエコシステムにとっても無視できない影響力を持っています。模倣か、革新か。その判断は外からは難しくとも、企業姿勢や透明性の発信が、その信頼を大きく左右することだけは間違いありません。