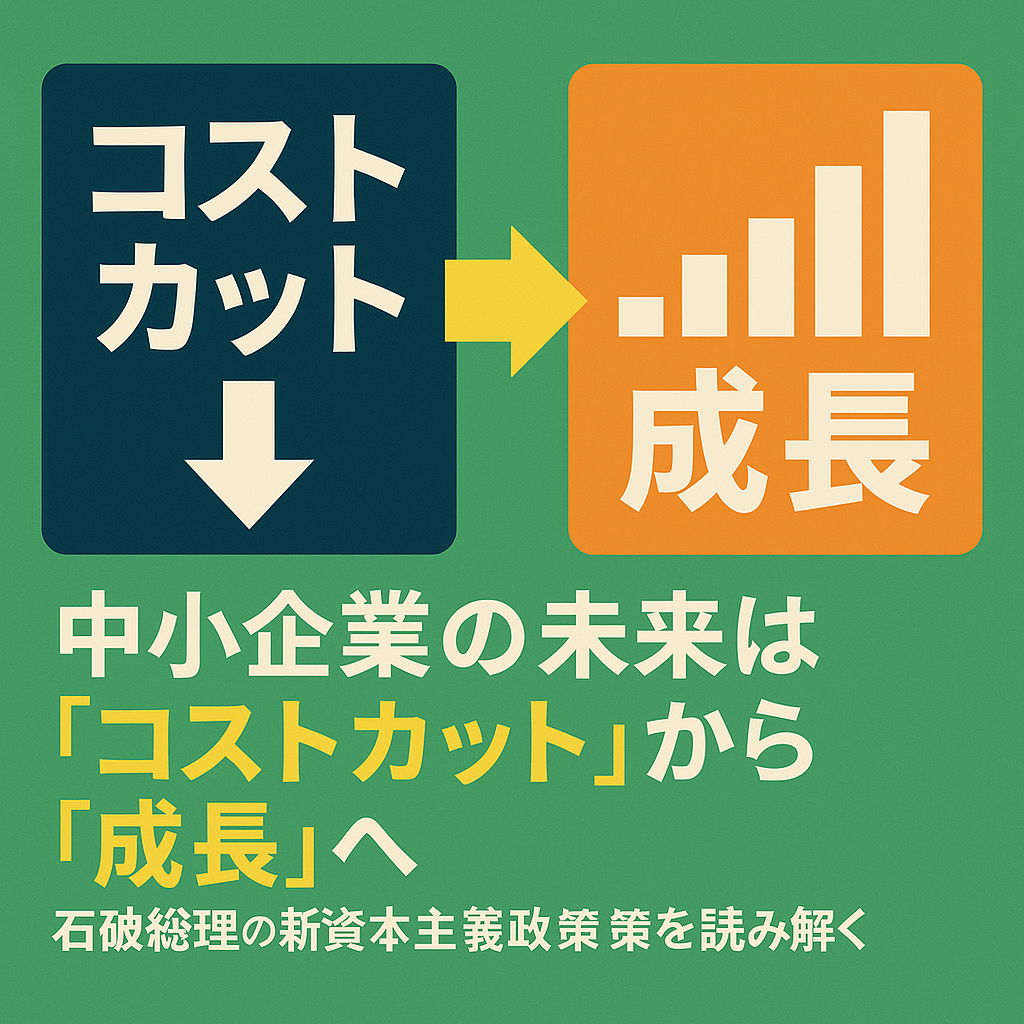2025年3月28日、石破茂総理が主導する「新しい資本主義実現会議」において、中小企業支援の大きな転換点となり得る政策方針が発表されました。キーワードは「コストカット型経営から成長型経営へ」。この一言に、今後の日本経済のあり方を占うヒントが詰まっています。
今回は、総理の発言と政策の3本柱を元に、その意図と影響を考察します。
「コストカット型経営」の限界と、その先にある成長型モデル
長らく日本の中小企業は「コスト削減」を軸に生き残りを模索してきました。安価な労働力、下請け構造、値引き交渉の連続――これはもはや成長戦略ではなく、疲弊戦略です。
石破総理が訴えたのは、この構造からの脱却。中小企業こそが賃上げ・投資・生産性向上によって「企業としての筋力」をつけ、経済全体を牽引する存在になっていくべきだというメッセージです。
政策の3本柱:期待と課題
- 価格転嫁と取引の適正化
価格交渉力を持たない中小企業が、原材料高や人件費増に耐えられずに沈んでいくのは本末転倒です。官公需における価格転嫁強化は、地域経済の屋台骨を守るうえで重要な一歩。
しかし、実効性は「現場の運用」にかかっています。大企業の買い叩きをどう監視するのか、価格交渉の透明性をどう担保するのかが問われます。
- 生産性向上支援と「省力化投資」
特にサービス業にフォーカスを当てたのは注目ポイント。人手不足が深刻な分野で、DX(デジタル化)や機械導入を後押しする「省力化投資促進プラン」は理にかなっています。
ただ、投資には当然リスクが伴います。「挑戦したくても資金が足りない」「成果が見えるまでが不安」という声に、国はどれだけ伴走できるでしょうか。
- 経営の見通しと事業承継支援
中小企業の最大の経営課題が「後継者不足」です。M&A支援の強化や信頼できる買い手とのマッチング支援は、地域の雇用や技術の継承に不可欠。
とはいえ、M&Aは信頼関係が全て。不適切な買収や買い叩きへの監視とガイドライン整備が、制度の成否を分けるでしょう。
「新しい資本主義」が問う、社会全体の価値観
今回の政策は、単なる中小企業支援策にとどまりません。根底には「企業は人を大切にし、投資して成長する」という、新しい経済倫理を根付かせたいという総理の意思が見えます。
成長とは、数字だけの話ではなく、「人が働きたいと思える職場」「地域に残りたいと思える産業」を育てること。この転換に社会全体がどう向き合えるか。私たち一人ひとりにも問われているテーマです。
まとめ
石破総理が掲げた「成長型経営」への転換は、中小企業にとってチャンスであり、試練でもあります。政策が現場で本当に血肉となるには、国の支援だけでなく、企業の意識改革、そして地域社会の理解と協力が欠かせません。
「コストを削る」のではなく、「価値を生み出す」経営へ――その第一歩が、今、始まっています。