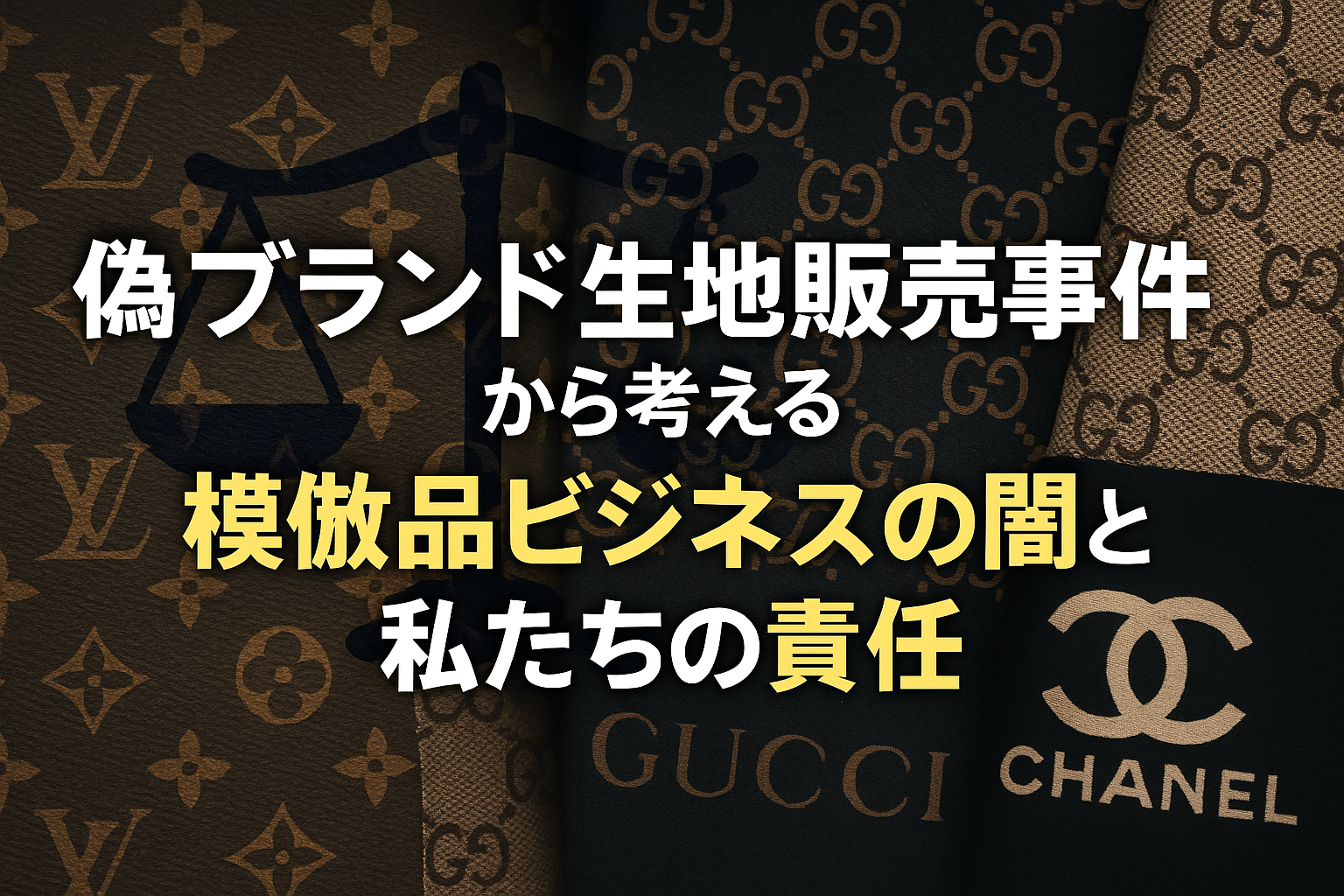2025年5月、ルイ・ヴィトンをはじめとする高級ブランドの偽ロゴ入り生地を所持・販売していた中国籍の女性が商標法違反で書類送検されました。報道によると、彼女は中国系のECサイトで偽物の生地を仕入れ、日本国内のフリマアプリなどで約580点を販売し、180万円近くを売り上げたとされています。
この事件の本質は「趣味」や「副業」の名の下で行われた知的財産の侵害です。容疑者自身、「違法と分かっていた」と供述しており、単なる無知による過失ではなく、故意による継続的な販売行為だったことが伺えます。近年、誰でも簡単にモノを売買できるフリマアプリの普及により、このような“素人による模倣品ビジネス”が温床になっている現実が明らかになりました。
特に今回のケースでは、「偽ロゴ入り生地」という一見“部材”として見過ごされがちなアイテムが焦点になっています。完成品だけでなく、素材段階での商標権侵害にも厳しい目が向けられていることは、今後のハンドメイド市場におけるルール作りにも影響を与えるでしょう。
また、消費者側の意識も問われています。価格が正規品と比べて明らかに安い場合、それが「なぜ安いのか」を考える視点が必要です。フリマアプリで“可愛いハンドメイドバッグ”を購入したつもりが、実は権利侵害に加担していた、というケースも起こり得るのです。
ブランドの価値は、長年の投資や信頼の積み重ねによって築かれるものです。それを不当に利用する模倣品の流通は、企業活動への深刻なダメージだけでなく、文化や産業全体の信頼性を揺るがします。今回の事件は、作る側・売る側・買う側それぞれが、「模倣品とは何か」「自分の行動はどんな影響を及ぼすのか」を見直す契機となるはずです。