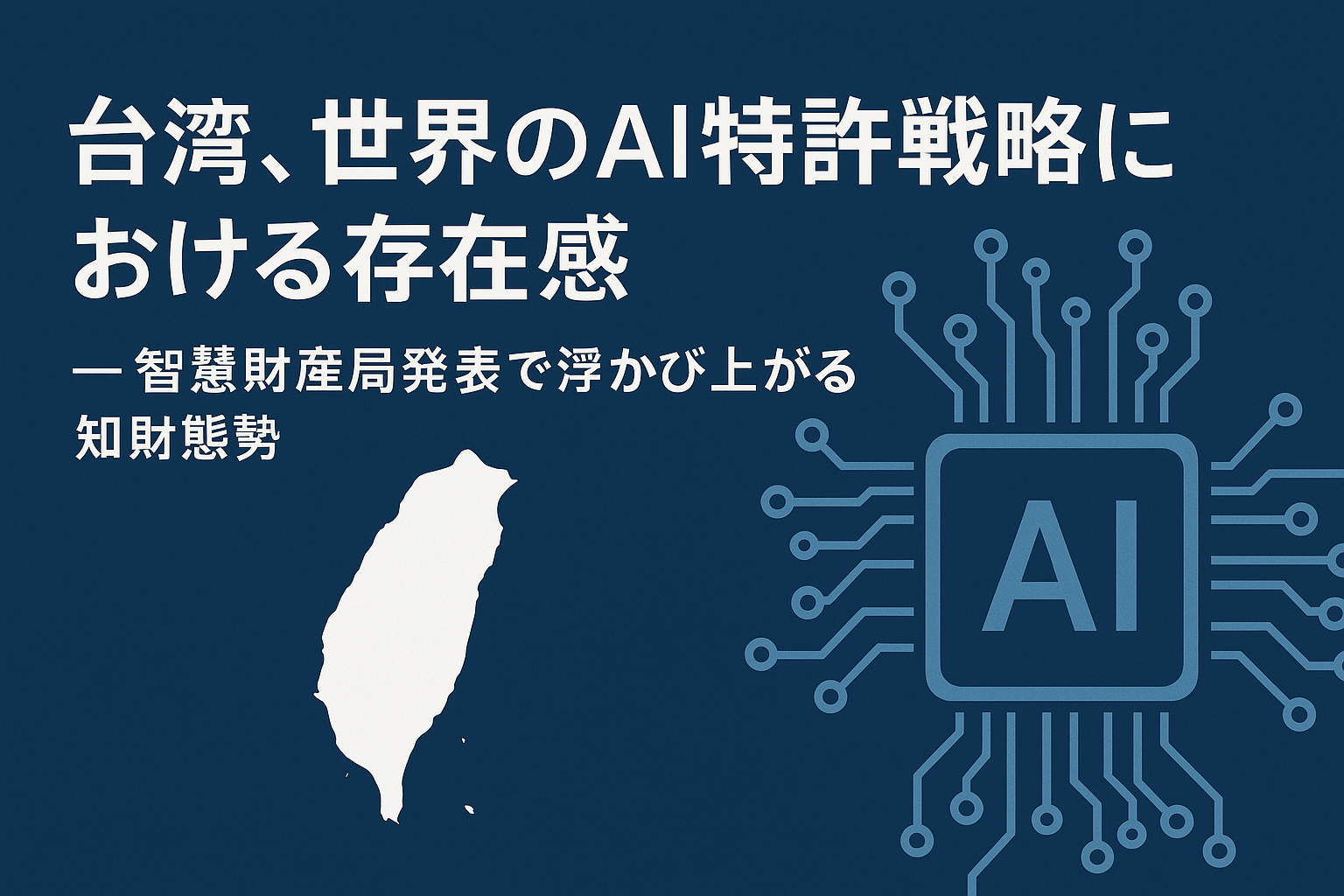ニュースの要点と意義
台湾の経済部管轄、智慧財産局(智財局)が23日発表した調査によると、人工知能(AI)関連の特許出願数で台湾が世界9位という位置を占めた、というニュースが報じられました。
このニュースは、単に順位の話に終わらず、知財/特許という観点から「台湾がAIの知財戦略におけるグローバルな拠点になりつつある」という同局のコメントからも、その意図・戦略性が読み取れます。
知財・特許を巡る世界的競争が激化する中で、台湾という“中規模”国家がAI特許分野で上位に入るという事実は、日本の知財担当者、研究機関、企業にとっても見逃せない情報です。
以下では、どうして台湾がこのようなポジションを確保しつつあるのか、データ・制度・産業という複数の観点から深掘りします。
台湾が世界9位の出願数に ― データと背景
ニュースによれば、同局が構築したグローバル特許検索システム(GPSS)を用いて、AI関連の技術を「ハードウェア/知識処理/機械学習/進化計算/機械視覚/自然言語処理/音声/計画・制御」の8分野に分類し、出願動向を分析しました。
台湾でも、2017年以降AI関連の出願数が大幅に伸び、2021年時点では2014年比で約9倍という急成長を見せ、機械学習の出願数では世界8位、機械視覚では9位にランクインしています。
このようなデータは、グローバルAI特許出願母数が過去10年で急増しているという報告とも整合します。
この“9位”という順位だけを取り上げるのではなく、成長ペース・分野特化・プレーヤー構成という点で意味を考えることが重要です。
どの分野で伸びているか:機械学習・機械視覚を中心に
同局の分析対象8分野のうち、台湾では機械学習と機械視覚関連の出願が特に多いとのことです。これは、世界全体でも機械学習・機械視覚分野がAI特許出願の大きな柱となっている事実と一致します。
例えば、「機械視覚」という言葉からは、カメラ・センサー・ディープラーニングを活用した視覚認識処理が想起され、台湾の強みである半導体・EMS(電子機器受託製造サービス)産業とも親和性があります。
つまり、台湾の特許出願が“量”だけではなく、“台湾の産業構造(ハードウェア・製造)+AIソフト/アルゴリズム”という二軸の統合によって伸びている可能性があります。
主な出願者と産学官の構図
ニュースでは、台湾から出願した企業・機関として、
- EMS世界最大手の 鴻海精密工業(フォックスコン)が1位
- 政府系研究機関の 工業技術研究院(ITRI)が2位
- 通信最大手の 中華電信 が4位
- 政府系シンクタンクの 資訊工業策進会(資策会)が7位
- EMS大手の 英業達(インベンテック)が9位
という顔ぶれが紹介されています。
この構図から読み取れるのは、「製造・ハードウェアの受託産業」「政府/公的研究機関」がAI関連特許出願を牽引しているという点です。ハードウェアを基盤に、AI機械学習・視覚処理といった技術を付加するという、台湾ならではの“製造+知能”タイプのモデルが浮かび上がります。
なぜ台湾なのか:地理・産業構造・知財制度の観点から
台湾がAI特許でこのポジションにある背景を、以下の視点から整理してみます。
- 製造/EMS強み
台湾には世界的に重要な半導体・電子機器受託製造(EMS)基盤があります。ハードウェア設計・製造・量産という強みが、AIハードウェア・機械視覚用途などに直結します。
- 知財制度&政策
例えば、台湾の 台湾特許商標局(TIPO)は、AI・デジタル分野への対応を進めており、AI関連の知財政策・ガイドラインが整備段階にあります。
- 産学官協力・政府プロモーション
政府機関・研究機関が出願上位に入っていることからも、戦略的な研究投資・知財意識醸成が進んでいると推察されます。
- グローバル拠点としての位置づけ
地理的にアジア・半導体・製造チェーンの中核に位置する台湾は、グローバルAI特許出願ネットワークにおいて“ハブ”的な役割を担えるというポジションを有しています。
つまり、単に「出願数が増えている」だけではなく、台湾の産業・制度・地理的アドバンテージが複合的に作用しているのです。
日本・アジア他国/グローバルとの比較視点
今回、台湾が「世界9位」というランクに入ったという点は興味深いですが、より広い視点から比べてみることも有用です。
グローバルでは、AI関連特許出願母数は急増しており、主要国の動向も注目です。例えば、ある報告では台湾は2020年時点で10,443件以上のAI関連特許を有していたとされ、規模以上の“パンチ力”を持っているという分析もあります。
一方で、出願数の“質”(引用度、国際展開、権利化率)や、AI生成物・AI発明者の知財制度対応などは、各国で成熟度に差があります。台湾でも「AIは発明者になり得るか」「AI生成物の著作権・特許の取扱い」など、制度整備途上のテーマがあります。
日本の企業・研究機関にとっても、台湾のこの動きは「隣国で知財競争が激化している」ことのシグナルと捉えるべきでしょう。
今後の焦点と知財リスク・戦略的意図
このニュースから今後注目すべき点、並びに知財リスク・戦略的な意図を整理します。
- 質の向上・国際展開
出願数を伸ばすだけでなく、先行技術・引用性・国際出願・実施可能性という観点でも評価が問われるため、台湾においても「量」から「質」への移行が鍵になるでしょう。
- 制度・法整備の進展
台湾では、AI発明者認定、AI生成物の知財保護・著作権認定、AIの倫理・データ利用規制などが制度整備の焦点です。知財の観点では、これら制度整備のタイミング・方向性を注視すべきです。
- 対外出願・グローバル戦略
台湾企業・研究機関が自国内だけでなく、海外(米国、欧州、日本、中国)へのAI特許出願・実施ライセンス展開をどう進めるかが焦点となります。
- クロスボーダー知財紛争リスク
台湾発のAI特許が日本・米国等での侵害訴訟・ライセンス交渉の起点となる可能性もあり、日本企業としては“台湾特許を無視できない”という認識を持つべきです。
- 日本企業の対応姿勢
日本企業・研究機関としては、台湾を“知財競合国”としてだけでなく、「共同開発/ライセンス・クロスライセンス」のパートナー視点も重要です。台湾の強み(ハードウェア・製造)×日本の強み(ソフトウェア・システム)という相補性の観点から知財戦略を再考する契機となります。
日本企業・研究機関にとっての含意
今回のニュースは、台湾が「AI特許出願数で世界トップ10入り」という数字を示したことに留まらず、産業・知財・制度の三位一体で“知財戦略的に生きている”国であることを示唆しています。
日本の知財/特許担当者、技術開発部門、研究機関は、台湾だけを見て対応を急ぐ必要はありませんが、「隣国の知財競争力の強化」を他山の石とすべきでしょう。
特に、AI・機械学習・機械視覚といった分野において、台湾企業や研究機関がどのように発明→出願→国際展開を進めるかをウォッチしながら、自社の知財ポートフォリオ・出願戦略・国際ライセンス戦略を改めて点検する好機と言えます。