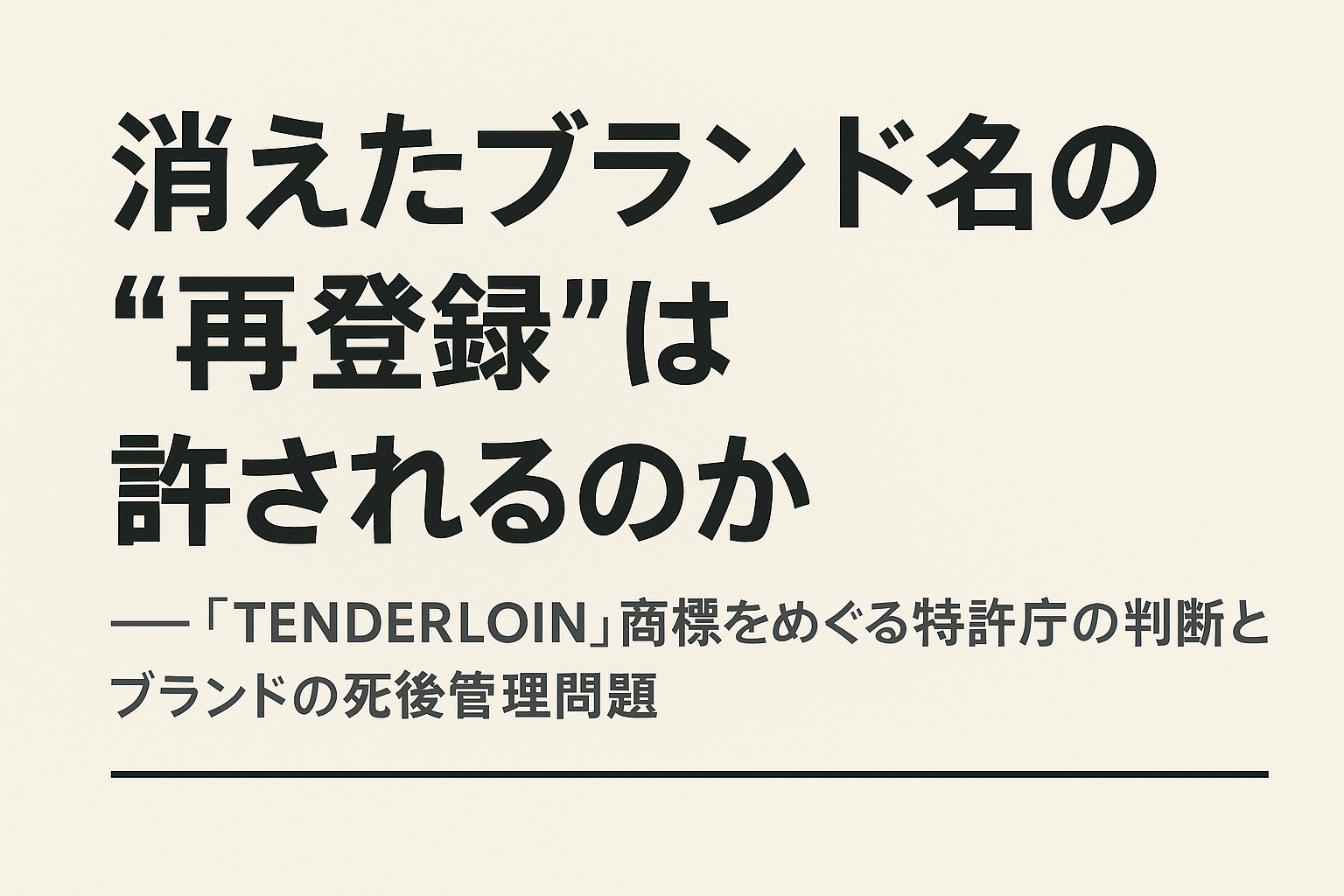かつての伝説ブランドが「第三者の手」に渡った
1997年に誕生し、木村拓哉さんら著名人の愛用でも知られたストリートブランド「TENDERLOIN」。
ファッション業界で一時代を築いた同ブランドは、2023年ごろまでに活動を終え、商標権も2022年11月に抹消されていました。
ところが2024年10月、「まったく関係のない企業」がこの商標を取得していたことが判明。出願人は「牛ヒレ肉」を意味する一般語としての使用を主張し、特許庁もこれを認めたのです。
特許庁は当初、「地名(サンフランシスコの地区名)であり識別力に欠ける」「旧ブランドの信用に便乗するおそれがある」として拒絶しましたが、最終的に“商標としての再利用”を認めた形です。
廃業ブランドの商標は「無主物」ではない
一度登録が抹消された商標は、理論上「誰でも再出願できる」状態になります。
しかし、商標法には不正目的による出願を排除する規定(第4条第1項第7号・第19号など)があり、他人の著名ブランドを“再利用”することは原則として認められません。
今回は、旧TENDERLOINが活動を終えており、ブランド認知も限定的と判断されたことで、拒絶理由を覆せたとみられます。
裏を返せば、「著名性が薄れた」と特許庁が判断したとも言え、かつての熱狂的ファンにとっては複雑な結論でしょう。
それでも「無効審判」で争える余地はある
登録が成立しても、その後に無効審判で覆される可能性があります。
旧ブランドの信用を利用して不正な利益を得る意図が認められたり、新しい商標の使用が品質誤認を引き起こす場合(例:粗悪な商品を「TENDERLOIN」名で販売する等)には、商標法第4条第1項第15号・第19号により無効となる余地があります。
ただし、旧ブランド側がすでに事業を終了している以上、「現実に損害が生じた」と立証するのは難しく、現行法の運用上は“放棄されたブランドの再取得”を完全に防ぐことは困難です。
ブランドの「死後管理」は新たな法的課題
今回の事案は、いわば「ブランドの死後」に関する知財の空白を突いた例です。
音楽や文学の著作権が死後も一定期間保護されるのに対し、商標権は更新を怠れば消滅する仕組みです。
ファッションブランドやスタートアップが活動を終える際、「ブランド名をどう守るか」「第三者による再登録をどう防ぐか」といった“終活的知財戦略”がますます重要になっています。
まとめ──「ブランドの余命管理」という視点を
TENDERLOINの件は、単なる“人気ブランドの再登録”問題にとどまりません。
それは、ブランドの余命をどう延ばし、どう安らかに終わらせるかという、知的財産のライフサイクル全体に関わる問いを投げかけています。
- 活動停止後もドメインや商標の管理を継続する
- 廃業時に明確な「商標処分方針(譲渡・維持・放棄)」を定める
- SNS上で「公式終了宣言」とともに第三者利用を明示的に禁止する
──ブランドの記憶を守るには、商標の登録以上に「管理の意思表示」が欠かせません。