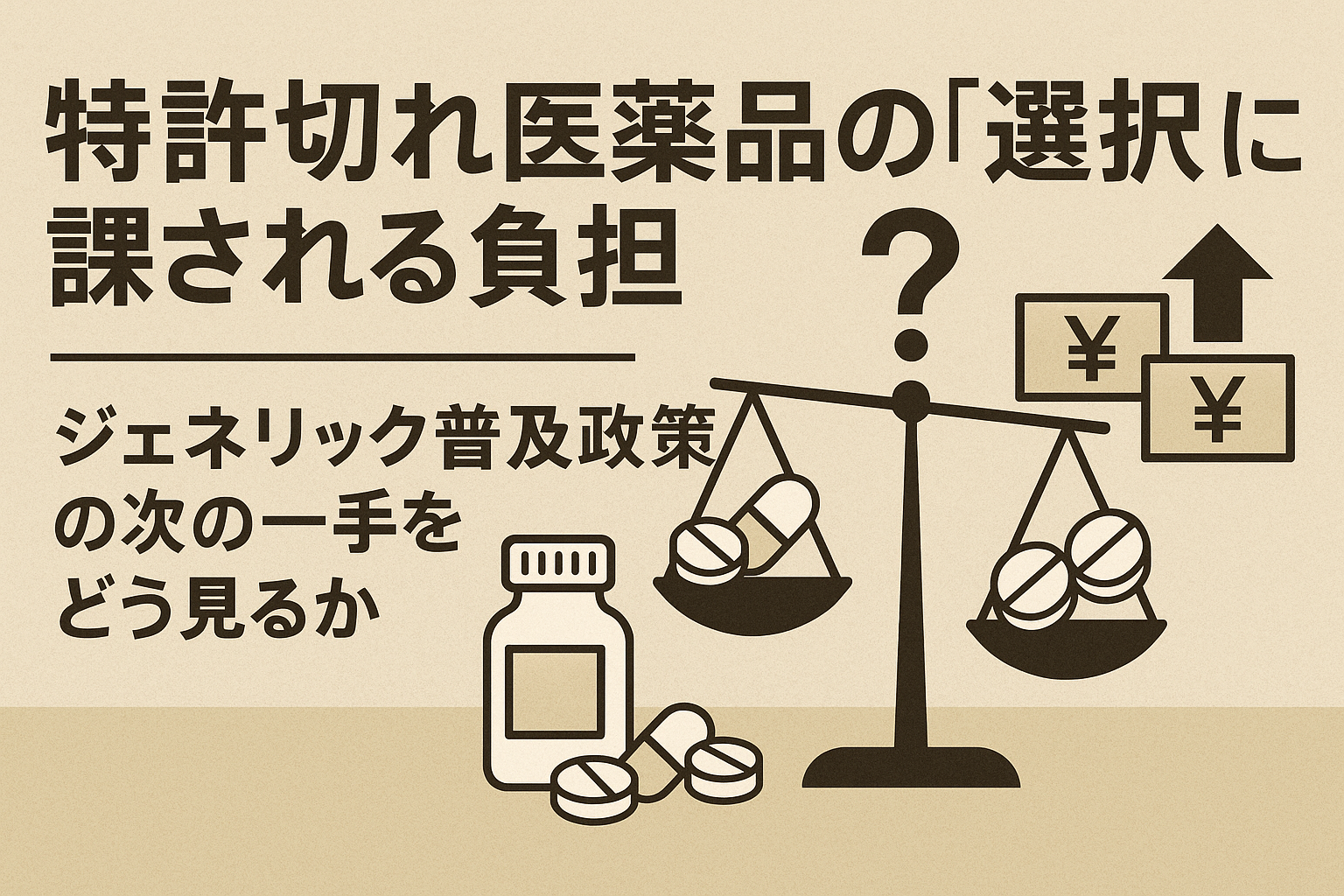厚生労働省が、特許が切れた先発医薬品の窓口負担をさらに引き上げる方向で検討に入りました。
すでに導入済みの「価格差25%上乗せ」制度を、50%~100%まで引き上げる案も俎上に載っています。
「選べる自由」と「政策誘導」の狭間で
制度の趣旨は明快です。
後発医薬品(ジェネリック)への切り替えを促し、医療費を抑制すること。
一方で、患者には「医師と相談して先発薬を選ぶ自由」が依然として残されており、追加負担はその“自由の対価”と位置付けられます。
しかし、これを「自由の尊重」ではなく「自由の制限」と受け止める声も少なくありません。
特に、後発薬の安定供給に不安が残る現状では、「選ぶ自由を事実上奪う政策」との批判が再燃する可能性があります。
「ジェネリック信頼回復」なしに進めば逆効果に
厚労省の議論で示されたように、供給の安定性は依然として課題です。
2020年以降の製薬企業不祥事や製造停止の影響で、ジェネリック市場の信頼は大きく揺らぎました。
その信頼が十分に回復しないまま、先発薬への追加負担を強化すれば、患者からは「不安な薬に誘導されている」と感じられ、政策全体の正当性を損ねかねません。
医療費抑制の“コスト”を誰が負担するのか
医療財政の観点から見れば、薬剤費削減は喫緊の課題です。
しかし、「公的医療費の節減=患者負担増」という単線的な構図が常態化することには慎重さが必要です。
ジェネリック普及による社会的利益を強調するなら、安定供給体制や品質管理の強化にこそ財政支援を振り向けるべきでしょう。
制度設計に求められる「信頼の順序」
特許が切れた薬に対して「先発薬を選ぶなら全額自己負担も視野に」という議論は、一見すると合理的に見えます。
しかし、医薬品の信頼性・供給体制・情報開示が追いつかないままでは、制度は“合理性”よりも“強制性”として映ります。
まずは信頼、その上で選択と誘導を。
それが、医療費抑制と患者の安心を両立させる唯一の道ではないでしょうか。