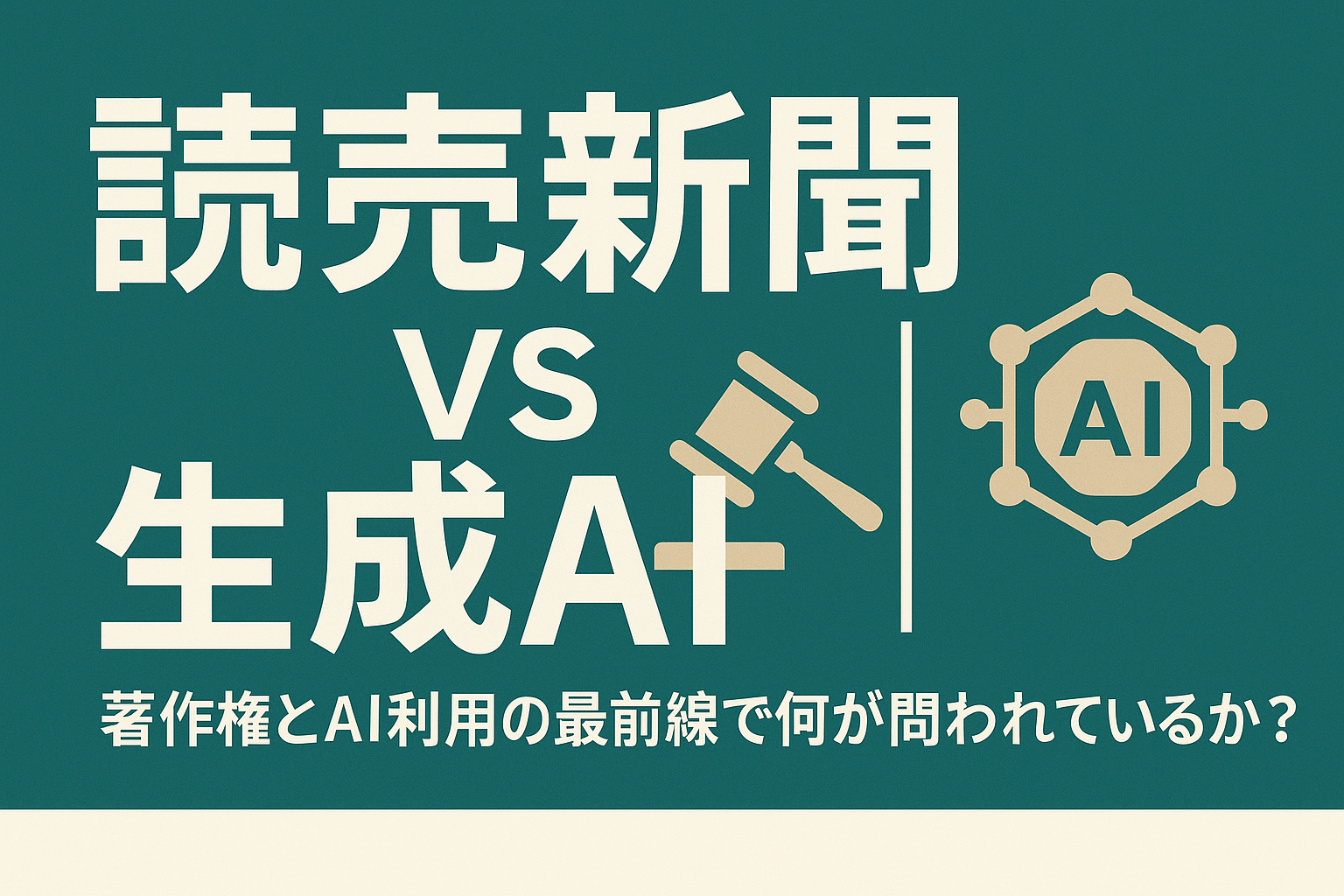2025年8月7日、国内の知的財産と報道倫理の両面において注目すべき訴訟が提起されました。読売新聞東京本社・大阪本社・西部本社の3社が、米生成AI企業「Perplexity(パープレキシティ)」を相手取り、記事の無断使用による著作権侵害を理由に、記事使用の差し止めと総額約21億6800万円の損害賠償を求めて東京地裁に訴えを起こしたのです。
何が問題とされているのか?
Perplexityは、AIを活用した検索サービスを提供しており、ユーザーの質問に対して複数のウェブ情報を統合・要約して回答します。これは一見便利なサービスですが、訴状によれば、読売新聞の記事約11万9,467件をオンライン上から無断で取得・複製したとされ、まさに「ただ乗り」だと読売側は主張しています。
記事という報道機関の知的資産を無断で吸い上げ、AIの学習や出力に使う行為が、著作権法に照らして許されるのかどうかが、この訴訟の核心です。
AIと著作権の衝突が本格化
生成AIは情報を「収集・分析・要約」するという構造上、既存の著作物に依存する側面が不可避です。しかし、その過程や出力が「引用」の範囲を超えている場合、著作権の侵害と見なされる可能性が高まります。
これまでにも海外では、米ニューヨーク・タイムズがOpenAIおよびMicrosoftを提訴した例がありますが、日本国内では大手報道機関が生成AI企業を提訴するのは初とされ、今後の裁判の行方は国内外の法制度の議論に影響を与えることが予想されます。
読売の主張──報道の信頼性が揺らぐ
読売新聞は「正確な報道に負の影響をもたらす」とし、AIによる記事の無断使用は、ジャーナリズムの根幹を揺るがすと強く批判しています。報道機関は取材・編集・検証といったコストをかけて記事を制作しており、それを無償で収集・再利用されることは、「報道インフラの共食い」に等しいとも言えるでしょう。
今後の焦点──法改正か、ビジネスモデルの転換か?
この訴訟が提起する論点は非常に広範です。
- AIによる「情報取得・再構成」はどこまで許されるのか?
- 公開されている記事でも無断複製は違法なのか?
- 生成AIに対する著作権の「使用料モデル」は確立されるべきか?
今後、日本の著作権法の改正やガイドライン整備が必要になる可能性もあります。一方で、AI事業者側も、報道機関などの権利者とライセンス契約や提携モデルを模索する動きが加速するかもしれません。
報道とAIは共存できるのか
生成AIの急速な普及に伴い、「知る権利」と「知的財産権」のバランスがこれまで以上に問われています。今回の訴訟は、単なる著作権の問題にとどまらず、情報社会のインフラをどう守り、どう進化させるのかという問いを私たちに突きつけています。
「AIのために報道がある」のではなく、「社会のために報道もAIもある」──その前提に立った冷静な議論と制度設計が今、強く求められています。