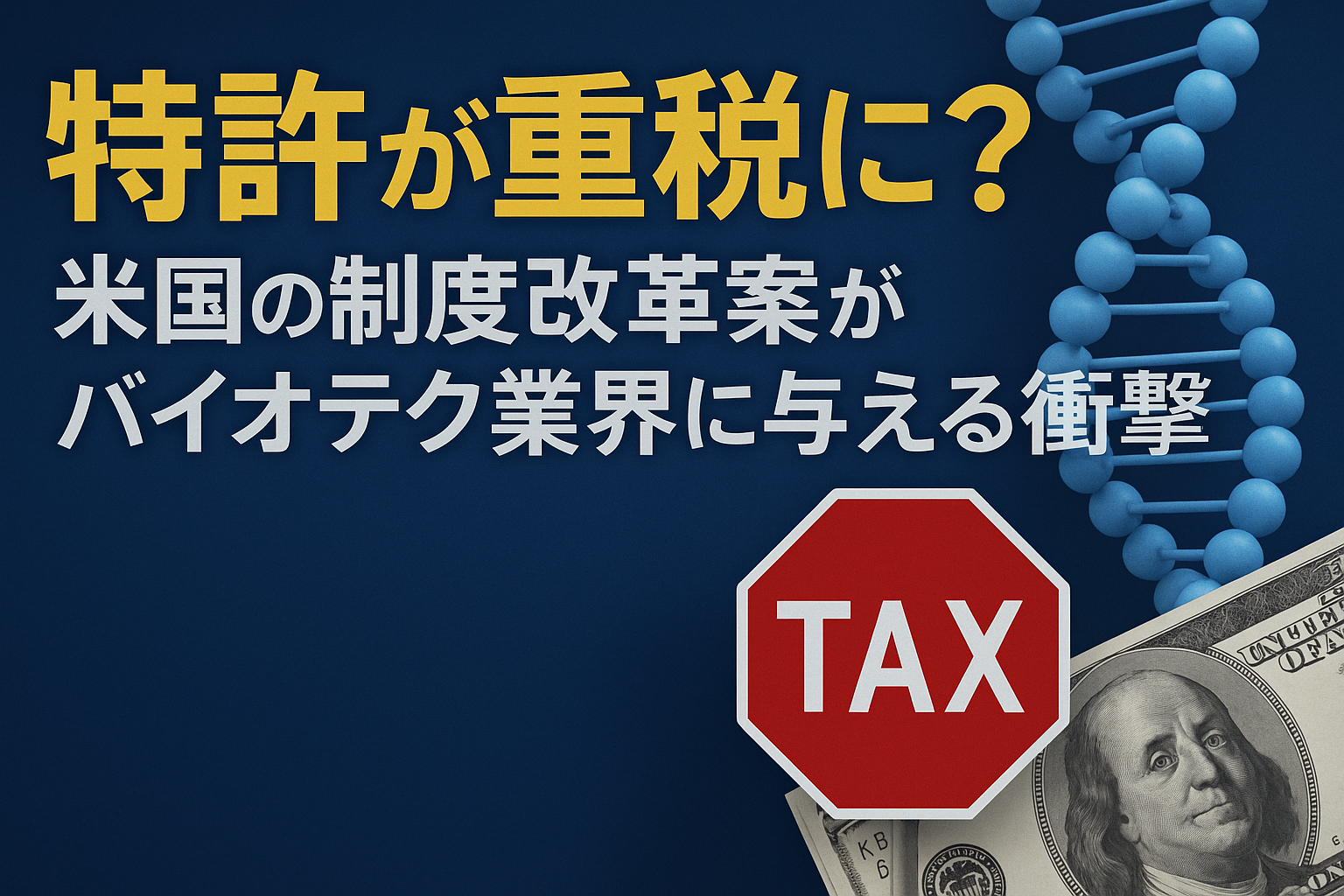米国商務省が検討している特許制度の抜本的改革案が、バイオテク業界に波紋を広げています。235年続いた制度の「定額制」から、「特許価値の1~5%課金」へ。もしこの案が実現すれば、知的財産に対する“事実上の財産税”とも言える構造に転換する可能性があり、研究開発に巨額の資金を投じるバイオテクノロジー企業にとっては死活問題となりかねません。
改革案の概要:知財課金の新たなモデル
ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、米国商務省は特許保有者に対し、特許価値の1%から5%を課金する新制度を検討中です。これは財政赤字削減の一環として提案されており、潜在的には数百億ドルの歳入増が見込まれています。
現在の米国特許制度では、特許保有者は比較的控えめな維持年金を支払うだけで済んでいます。新制度はこの「固定費モデル」から「価値連動モデル」への転換を意味し、特許が高い収益を生むほど負担も重くなる構造です。
制度改革の本質:税か、公正な見直しか?
今回の改革案は「知的財産への課税」とも捉えられますが、一方で「過度に特許に依存した利益構造への是正」と見る見方もあります。ビッグファーマの高額薬価問題などを背景に、特許制度への批判が高まっているのも事実です。
しかし、イノベーションの源泉を圧迫する制度改正は、短期的な歳入増と引き換えに長期的な技術競争力を損なうリスクがあります。バランスある議論が求められます。
今後の展望と日本企業への示唆
現時点ではあくまで「協議段階」であり、制度化されるかどうかは不透明です。ただし、仮に米国でこのような制度が導入されれば、国際的な特許政策にも影響を与えることは間違いありません。
日本の製薬・バイオ企業も米国で特許を取得しているケースが多く、コスト増の影響を受ける可能性があります。また、知財政策が国際競争力と直結する時代において、日本も自国の制度設計を見直すべき局面に立たされるかもしれません。
特許制度の変更は、単なる技術管理の問題ではなく、イノベーションの根幹を揺るがす経済・政治の問題でもあります。知的財産の重税化は、目先の収入確保以上に、未来の成長戦略を犠牲にする危険をはらんでいます。バイオテク業界、そして知財戦略に携わるすべての関係者にとって、今回の動向は無視できない重大なシグナルです。