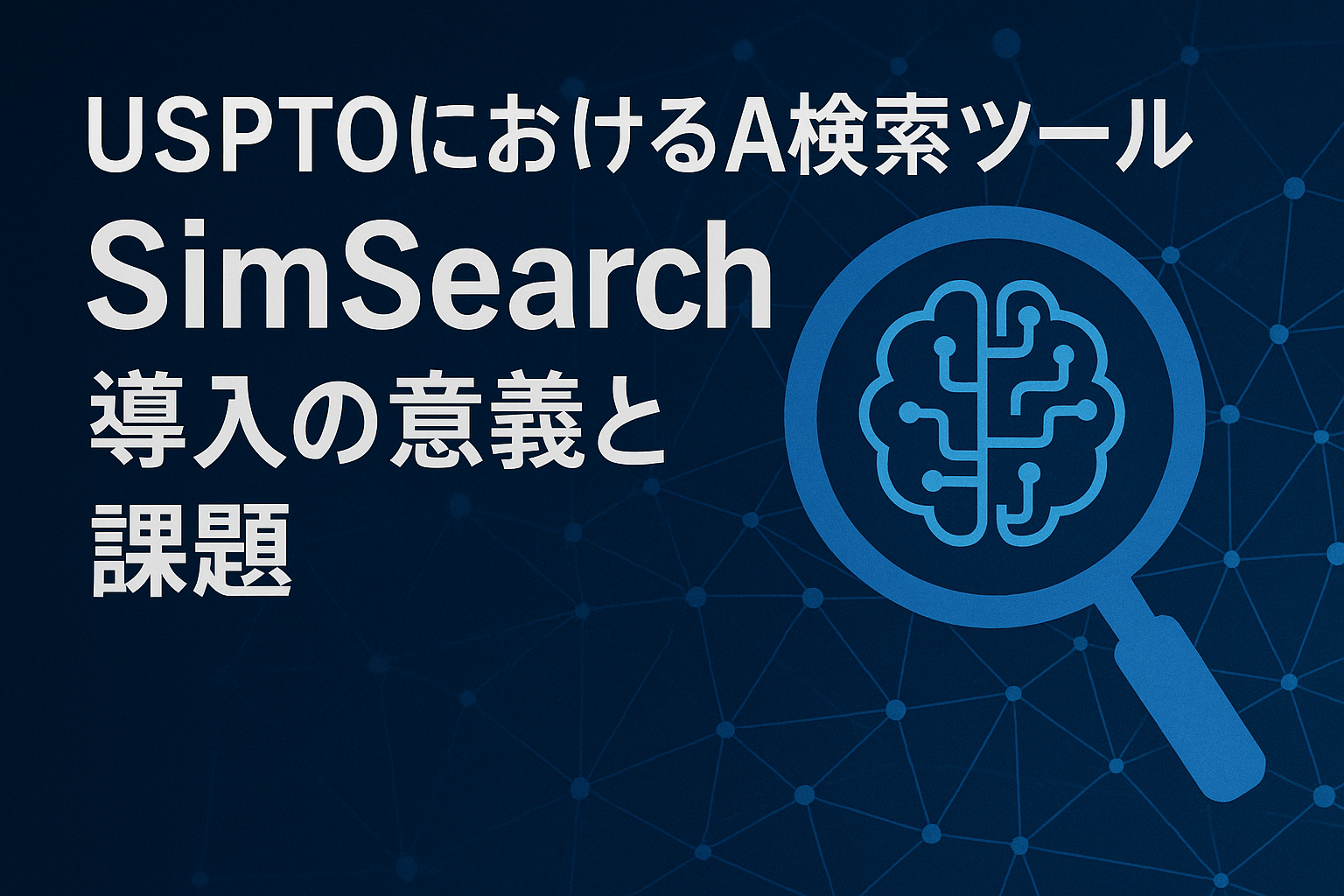2022年9月以降、米国特許商標庁(USPTO)の特許審査官は、新たにAI支援型検索ツール「Similarity Search(SimSearch)」を活用できるようになりました。これは特許出願のテキストを基に自動的に検索クエリを生成し、関連度の高い文献を提示する機能です。従来の検索を補完する形で導入されており、審査官は検索結果の利用可否を自由に判断できます。
SimSearch導入の意図
特許審査の核心は「先行技術調査(prior art search)」にあります。従来のキーワード検索では、出願文言と先行文献の表現の違いが障壁となり、重要な先行技術を見落とすリスクがありました。
SimSearchは自然言語処理(NLP)と機械学習を組み合わせ、単純なキーワード一致に留まらず、意味的な近似性に基づいた文献抽出を可能にします。これにより、審査の網羅性と効率性の向上が期待されています。
実務上のメリット
- 効率性の向上
出願テキストから自動的にクエリが生成されるため、検索式作成に要する時間を削減できます。特に、改訂後のクレームにも迅速に対応できる点は大きな利点です。
- 調査精度の向上
単なる文字列一致に依存せず、「意味的に類似した文献」を抽出できるため、従来なら見落とされがちな先行技術を発見する可能性が高まります。
- 柔軟な調整機能
- 出願の特定部分を強調して検索を行えるため、技術的焦点に沿った調査を容易に実現できます。
想定される課題
一方で、いくつかの懸念も指摘できます。
- ブラックボックス性
AIモデルがどのように関連度を算出しているかは不透明であり、審査官や出願人の納得性に影響する可能性があります。
- バイアスのリスク
学習データの偏りにより、特定の技術分野や文献に検索結果が偏る可能性があります。
- 責任所在の問題
- SimSearchは補助ツールであるとされますが、結果を採用するか否かの判断は審査官に委ねられます。この「最終判断の責任」は依然として人間が負う点を明確化しておく必要があります。
今後の展望
SimSearchはまだ始まりに過ぎません。将来的には、
- 出願人や代理人にもAI検索を開放し、調査の対称性を確保すること、
- 国際的な審査機関間でAI検索基盤を共有すること、
- さらには検索結果の透明性向上と審査官教育の強化、
といった展開が期待されます。
AIは「審査官を置き換える存在」ではなく、「審査官の能力を拡張する存在」として導入されつつあります。SimSearchの運用成果は、AIと人間がどのように協働できるかを示す試金石となるでしょう。特許制度の信頼性を損なうことなく効率と精度を高められるか──今後の運用と改善が注目されます。