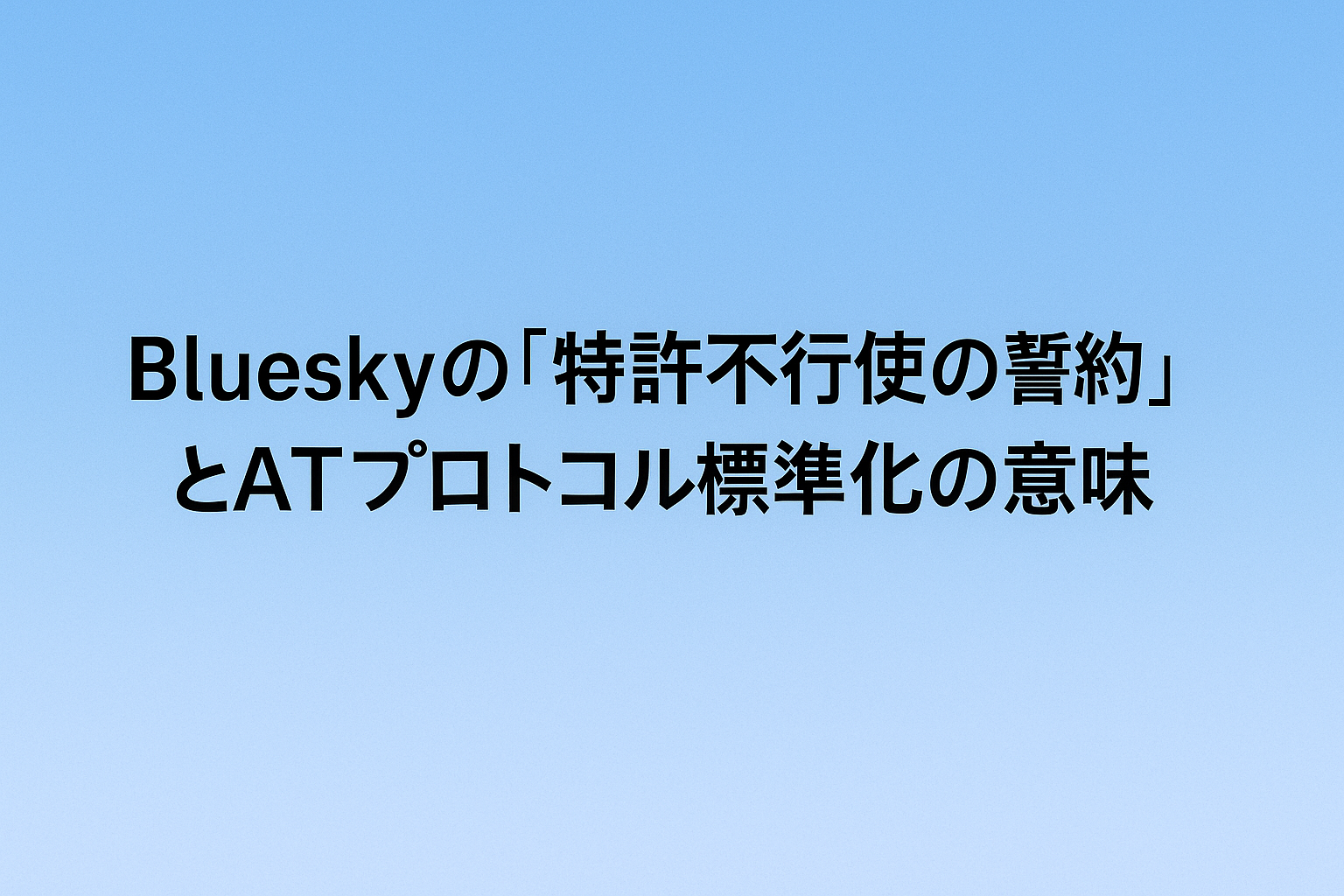分散型SNS「Bluesky」が、サービスの基盤となるATプロトコルの一部をインターネット標準化に向けてIETFに提案しました。同時に発表されたのが「特許不行使の誓約(Patent Non-Aggression Pledge)」です。これは単なる技術的な取り組みにとどまらず、分散型インターネットの将来像に直結する重要な一歩といえます。
特許不行使の誓約とは何か
Blueskyは「現在または将来保有するソフトウェア関連特許を他者に対して行使しない」と明言しました。ただしこれは無条件の放棄ではなく、防御的な利用は残しています。つまり、第三者がBlueskyに対して特許侵害訴訟を仕掛けてきた場合に限って、Bluesky側も特許を盾に反撃できるという仕組みです。
このスタンスはオープンソース界隈で時折見られる「条件付きの特許不行使」モデルと同じ系譜にあり、安心してプロトコル実装に取り組める環境を生み出すことを狙っています。
なぜIETFへの提案が重要か
IETFはインターネット技術標準化の中心的な存在です。TCP/IPやHTTPといった、いまや誰もが日常的に使っているプロトコルもIETFで策定されてきました。BlueskyがATプロトコルをIETFに持ち込むということは、「分散型SNSの技術をインターネット標準の一部にしたい」という強い意思表示にほかなりません。
分散型SNSの広がりと課題
MastodonやMisskeyのようなFediverse系サービスが広まりつつある一方で、プロトコルの乱立が課題とされています。ATプロトコルが標準化されれば、相互運用性の向上や開発者の参入障壁の低下につながり、分散型SNS全体の成長を後押しする可能性があります。
考察:Blueskyの戦略と未来
今回の誓約は、単に「技術を開放する」というだけでなく、「法的な安心感」をパッケージにして示すことに価値があります。特許リスクを気にせず開発できる環境は、スタートアップや個人開発者を巻き込むうえで決定的に重要です。
インターネット標準は「時間がかかるが長期的に強固な基盤」になります。Blueskyがそこに賭けたという事実は、単なる一SNSサービスを超えた、インターネットのインフラ層を担う野心を表しています。
まとめ
Blueskyの「特許不行使の誓約」は、オープンプロトコルの普及における大きな安心材料です。そしてIETF標準化を目指す動きは、分散型SNSが「一時のトレンド」から「次世代インターネットの本流」へと進化していく可能性を示しています。