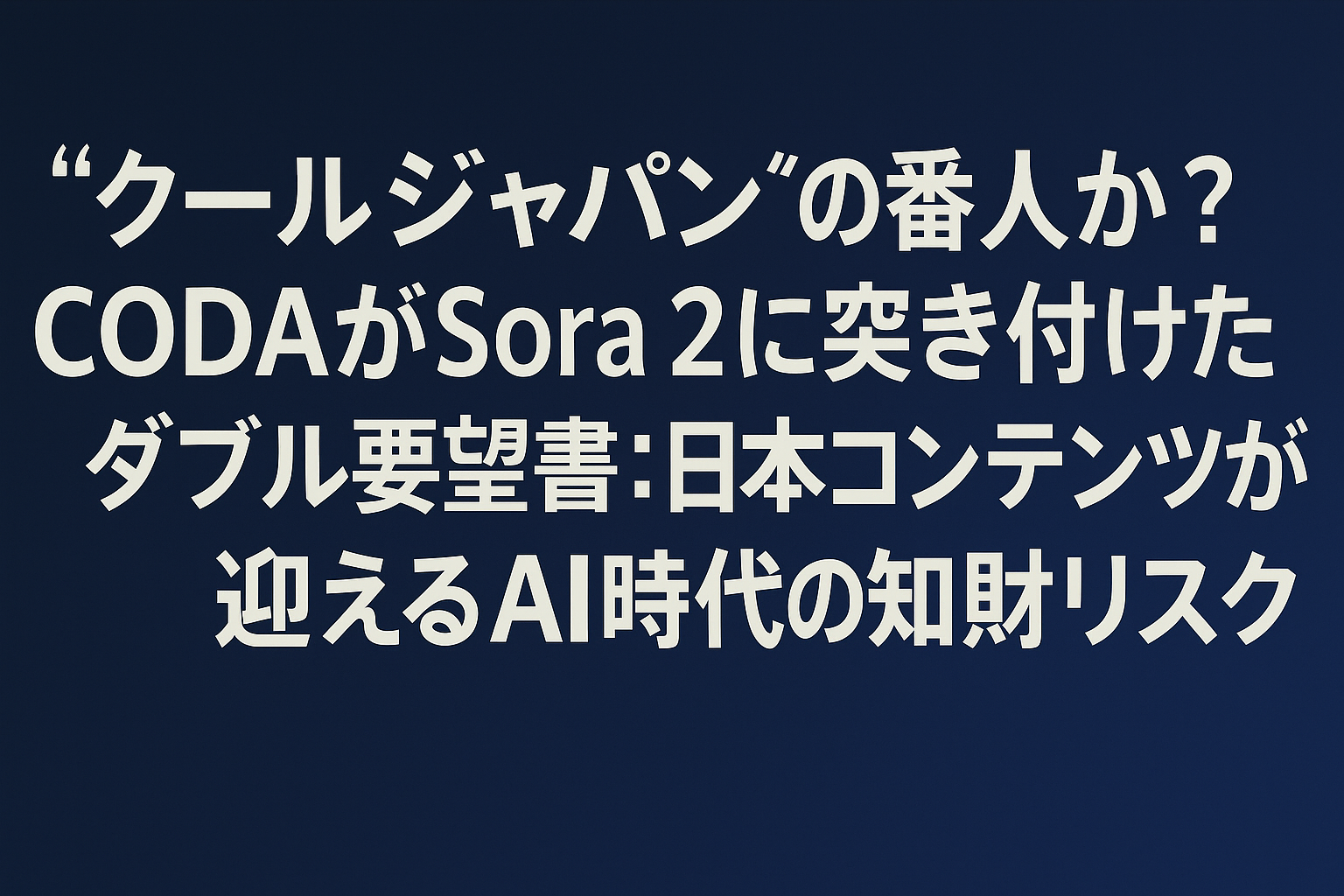10月28日、出版社やアニメ制作会社など36社が加盟する団体CODAが、米 OpenAI の動画生成AI「Sora 2」に対し、「日本の既存コンテンツまたはそれに酷似する映像が多数生成されている事実を確認した」として、① 無許諾学習の停止、②生成物に関連する著作権侵害申立て・相談への誠実対応、という2点を要望書として提出しました。
この動きは、単なる企業間の主張にとどまらず、「コンテンツ立国」日本が AI 生成技術とどう向き合うかを示すひとつの指標になり得ます。
なぜ今、CODA が動いたのか
- Sora 2の技術特性/波及
Sora 2は昨10月1日(発表)に公開された動画生成AIで、前モデルより「物理法則に忠実に動く映像」を作成可能とされており、SNS上には「人気アニメ『鬼滅の刃』『ポケットモンスター』などの日本IPに酷似する動画が生成された」旨の報告が出ていました。
報道では、Sora 2は「著作権者がオプトアウトしない限り、著作物を学習対象とし得る仕様」であったとされます。
- 日本のコンテンツ産業の立ち位置
日本はアニメ・マンガ・ゲーム・出版といった文化コンテンツを世界に誇る輸出資産と位置付けており、CODAはその海外流通促進および著作権侵害防止を目的に活動しています。
その意味で、国内IPがAIによって無許諾で「生成・模倣」される可能性は、単なる権利者の懸念にとどまらず、国家文化戦略・ブランド戦略上も大きなテーマです。
- 法制度・既存の著作権枠組みとのズレ
CODA の声明では、「日本の著作権制度では原則として利用に事前の許諾が必要であり、事後異議申し立てによって侵害責任を免れる制度は存在しない」と指摘しています。
つまり「オプトアウト方式」が前提となっていたSora 2の運用方針は、少なくとも日本国内制度との齟齬を含む可能性があります。
この要望書から見える争点・焦点
- 学習データとしての既存コンテンツの扱い
AIモデルの学習時点で、既存著作物(動画・アニメ映像・マンガ絵など)を利用したら、それ自体が「複製行為」として著作権侵害となる可能性があるというのが、CODAの主張です。
ここでは、「入力」と「出力」の両方が争点になります。学習入力段階の無許諾利用と、出力段階で既存コンテンツに酷似・再現されるという二重構造。
さらに、「酷似」していなくてもスタイル模倣・キャラクター類似といった“派生的生成”が、どこまで許されるのかというグレーゾーンがあります。
- オプトアウト方式 vs オプトイン方式
Sora 2の運用では、著作権者が除外申請(オプトアウト)しない限り利用を許すという方式がとられていたと伝えられています。
これに対し、CODAおよび日本政府は「利用には事前の許諾が原則」という立場を強調。つまり、オプトイン(許諾を得てから利用)に近づけるべきという主張です。
この対立から、AIモデル運用の倫理・制度設計という新たな枠組みが浮かび上がっています。
- 国際格差・文化輸出としての視点
興味深いのは「米国のキャラクター(例:ディズニー・マーベル)はSora 2では出力できないのに、日本のコンテンツは出力できた」という指摘。
ここには“日本のコンテンツが格下扱いされたのではないか”という文化・産業的な危機感が含まれています。ソフトパワーとしての日本IPがAIによって無許諾利用されるという構図は、内外で波及的インパクトをもつ可能性があります。
- 権利者対応・制度整備の必要性
CODAの要望書には「生成物に関連する著作権侵害について、会員社からの申立て・相談に真摯に対応すること」という条項があります。
これは、生成AIが出力する“ファン・コンテンツ/模倣コンテンツ”に対して、権利者がどう対応できるかという実務的な問いです。削除請求、収益分配、使用モニタリング、法的責任の所在…といったテーマが浮上します。
今後の展望・示唆
- 国内制度改正の可能性
日本政府は、今回の件を契機に、AI Promotion Act(AI 促進法)などを通じて、「AIによる著作物利用の枠組み」整備を進めています。
例えば「事前許諾の制度化」「学習データ開示義務」「生成物のフィルタリング義務」「収益モデルへの権利者の参画」などが検討対象となるでしょう。
- コンテンツ権利者の交渉力強化
権利者側は、AIモデルに対する学習データ提供の可否、生成物の商用利用に対する収益分配、キャラクター使用管理にかかる契約条件など、新たな契約モデルを構築する必要があります。
特に、国内アニメ・マンガ業界は“クールジャパン”戦略の主役であるため、国際的な交渉力・制度設計力を高めることが急務です。
- AI事業者の対応変化
事実、OpenAIはSora 2発表後、CEO Sam Altman が「日本のクリエイティブへの敬意」とともに、キャラクター生成をより細かく制御できる仕組みや収益を得られる仕組みの提供を表明しています。
今後は、AI生成サービスが「権利者とのライセンス・コラボレーション型モデル」へ舵を切る可能性が高いです。ただし、実務的な運用(学習データの管理・除外・生成物モニタリング等)は難易度が高く、継続的な課題です。
- クリエイター/ユーザー側の意識変化
AI生成/模倣コンテンツが拡大する中で、クリエイター側(アニメーター・漫画家・ゲーム開発者など)は「自らのスタイル・キャラクターがAIに利用され得る」リスクを意識し始めています。
一般ユーザーも「好きなキャラクターで動画作れる時代だが、背後にどのような権利処理があるか」を知る必要があります。透明性がカギとなります。
- 国際的影響・先例化
日本のこの動きは、欧米・アジア諸国にとっても参考となる“生成AI×著作権”の先行事例です。特に、文化輸出型のコンテンツ産業を抱える国々にとって、日本の制度対応・交渉成果は目が離せません。
また、AIモデル運用者にとっては「学習データの権利クリアランス」「生成物の利用契約」「責任所在の明確化」が国・地域ごとに異なる制度対応を要求されるフェーズに入ったと言えます。
今回のCODAによる要望書提出は、単なる企業間調整に留まらず、以下のようなメッセージを含んでいます。
- 日本のコンテンツ産業が、AI時代においても「許諾利用」「契約モデル」「クリエイター保護」の原則を維持・強化しようとしていること。
- 生成AIという技術進化が、著作権制度・文化政策・コンテンツ産業構造を再定義しようとしている転換点であること。
- AIビジネスのグローバル化が進む中で、日本が「自国IPを守る」だけでなく、「国際ルール形成」においても主体性を持とうとしていること。
知財・コンテンツ業界に携わる者、特にアニメ・マンガ・ゲームといった“キャラクター資産”を持つ企業・クリエイターにとって、今回の動きは“対岸の火事”ではありません。学習データの扱い、生成物の収益化、利用ルールの明確化—これらが今後のビジネスモデルに重大なインパクトを及ぼす可能性があります。