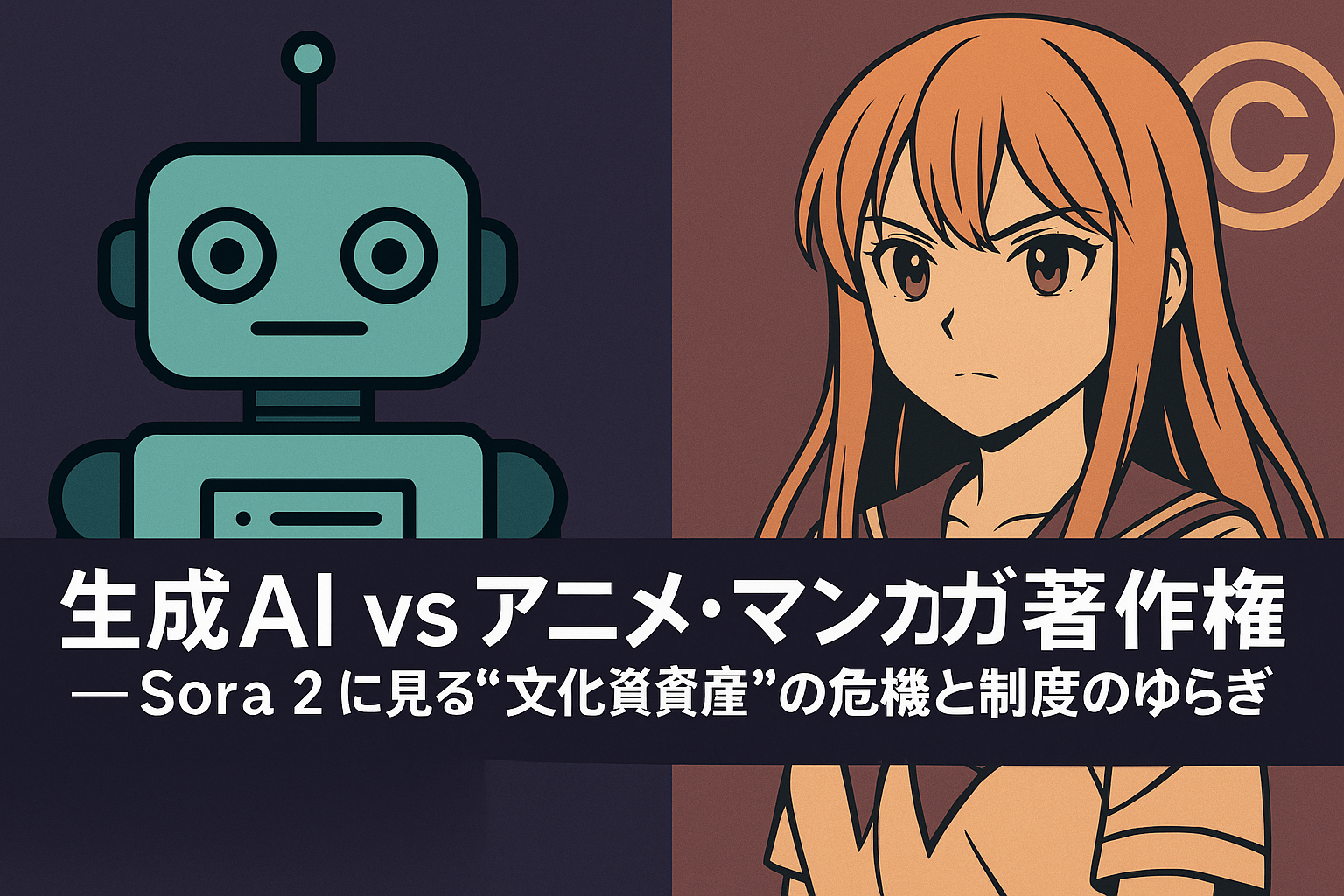背景とニュースの整理
米IT企業が開発した生成AI「Sora 2」を使って、日本のアニメなどのキャラクターが動画として生成・インターネット上に公開されているという問題が起きています。
この状況を受け、国内大手出版社等を含む19社・団体が「生成AIによる著作権侵害を容認しない」とする共同声明を発表しました。
声明では、
- 権利者に必要な許諾を得ること
- 学習データの透明性確保
- 利用を許諾した場合、権利者への適正な対価還元
といった対応をAI事業者が行うべきだと明記しています。
また、「使用されたくない場合に権利者側から除外意向を伝えなければならないという仕組み」は、そもそも権利侵害につながりうると批判しています。
一方で、OpenAI側はSora 2で「キャラクターなどがどのように使われるか細かく指定できる機能を導入する方針」をCEOの Sam Altman が明らかにしています。
なぜ日本のアニメ・キャラクターが焦点になったのか
以下のような理由が考えられます。
- 日本のアニメ・マンガは国内だけでなく世界的にも文化的ブランドとして認知されており、「文化資産」としての価値が高い。例えば、政府側も「アニメ・マンガは“替えのきかない国の財産”」と発言しています。
- 生成AI「Sora 2」による動画生成の中で、明確に日本のアニメ・ゲームのキャラクター(例:Nintendo/ポケモン作品等)が登場しているという報道があります。
- 日本の著作権制度では、一般的に「事前の許諾」が必要とされるため、AI事業者が「許諾なく利用・学習させた可能性」が批判を受けやすい構造があります。
- クリエイター・出版社・マンガ家協会といった国内の権利者側の反応が比較的早く、共同声明という形で制度的な対応を模索し始めたことも影響しています。
このように、単に「AIができちゃった」だけではなく、日本のコンテンツ産業、文化的価値、制度的構造がこの問題を浮き彫りにしていると言えます。
問題の本質:生成AIと著作権のズレ
このニュースを通じて浮き彫りになる問題を整理すると以下のようになります。
- 学習データ・生成出力と著作権の関係
生成AIは大量の既存データ(画像、映像、音声、テキストなど)を学習して出力を生成します。
問題となるのは、学習に用いられたデータが著作物(キャラクター、アニメ、ゲーム等)であった場合、その学習や生成出力が「著作権侵害」になりうるかという点。
日本の制度では「複製」「翻案」「公衆送信」等が著作権侵害となりますが、AIによる生成・流通のプロセスが従来の枠組みに即しているかは、明確ではありません。
- 事前許諾 vs 事後除外(opt-out)モデルの対立
本件の論点の一つに、権利者が「使用されたくない」という意思表示をしなければならない(=事後除外=opt-out)モデルをAI事業者側が採用していたことがあります。
これに対し、権利者側は「使われたくないなら自ら除外を申し出るべき」という仕組み自体が問題と捉え、「事前許諾=opt-in」が適当であるという立場をとっています。
つまり、AIモデルが許諾なしに利用データ/出力対象を含む可能性があるという点が、制度的なズレとして浮き彫りです。
- 対価還元・透明性の課題
権利者の関与なしに生成AIが既存のキャラクターやスタイルを生成可能とすると、権利者が収益機会を逃す可能性があります。
声優・キャラクター利用・ブランド価値という観点から、「生成AIを使った動画・映像からどう還元を図るか」が関心の的です。
さらに、AI学習に使われたデータの出所・透明性が担保されていないケースでは、権利者が “知らないうちに” 自分の作品が生成対象になっていた、という問題も生じています。
- 文化資産としてのアニメ・マンガの価値とグローバル展開
日本のアニメ・マンガは海外展開も活発であり、権利管理・ブランド管理・二次創作文化といった要素が複雑に絡んでいます。
生成AIによって“既存キャラクター+新規設定”という動画が簡易に量産されると、原作のブランド価値低下や権利混乱が起こりうるという懸念があります。
その意味で、「文化資産をどう守るか/どう活用するか」という視点も不可欠です。
出版社・関係団体が出した共同声明の意義
ニュースによれば、19の企業・団体(出版社やマンガ家協会など)が共同声明を発表し、以下のような主張をしています。
- 著作権侵害を容認しないという原則を確認。
- AI事業者は、権利者に許諾を求めること。
- 学習データの透明性を確保。
- 許諾する場合、権利者に適正な対価を還元。
- また、「権利者が除外希望を伝えなければならない」仕組みは権利侵害につながりかねないため、使用許諾を得ることの徹底を求める。
この声明の意義として、以下が挙げられます。
- 権利者側が共同で “AIに対する立ち位置” を明確にした点。
- 単なる反発ではなく、「透明性」「適正対価」といった建設的な要求を挙げている点。
- 国際的な生成AIの動きに対して、日本コンテンツ産業が制度対応・ガバナンスの枠組みを模索し始めているというメッセージ性。
- また、声明が「除外の仕組み」ではなく「許諾の仕組み」であるべきという原則を示している点で、制度設計の方向性を示唆しています。
シンプルに言えば、「後追いで除外を言えば良い」という状況ではなく、「そもそも許諾を前提とし、透明性と適正還元を確保する」という新しい契約・制度思想を提起しているわけです。
生成AI事業者(OpenAI)の対応と限界
事業者側、特にOpenAIの対応を整理すると以下の通りです。
- Sora 2のリリース直後、多くの動画生成例がアップされ、その中に日本のアニメ・ゲームキャラクターを模したものが含まれていたという報道があります。
- OpenAIは初期の方針として「権利者が除外を希望する場合に申し出る(opt-out)モデル」を採用しており、権利を明示的に除外しなければ利用可能という形でした。
- しかし、国内外からバッシングを受け、特に日本政府からも「アニメ・マンガは替えのきかない財産」として対応を求められています。
- それを受け、CEO Sam Altman は「キャラクターなどの利用に関して、より細かな制御機能を導入する予定」と表明しました。
とはいえ、限界・課題も明らかです。
- 権利者に対する「許諾取得の義務化」や「初期データの使用許諾」などの制度的義務が明確に存在しているわけではなく、グレーゾーンな状況です。
- 学習データの出所・権利クリアの可否・生成出力の“著作類似性”をどう判断するかといった技術的・法制度的課題が未解決です。
- 「細かな制御機能」を導入するといっても、実際にどこまで実効性を持たせられるか疑問があります(大量生成/SNS拡散のスピードには制度が追いついていない可能性があります)。
- コンテンツを守る側(出版社、クリエイター)と、プラットフォーム・技術提供側(AI企業)の力関係・契約交渉力のバランスにも課題があります。
つまり、事業者が対応を打ち始めたとはいえ、「生成AI×著作権」という領域では制度・技術・ビジネスの三者がまだ調整中であり、予断を許さないフェーズにあります。
今後の展望と我々クリエイター/ビジネス側が取るべき視点
この問題を踏まえ、「今後、どのような視点を持つべきか」を整理します。
- クリエイター・権利者側視点
自分のキャラクター・作品が生成AIによって如何に使われ得るかを再点検し、「許諾を出す/出さない」の意思統一をしておく必要があります。
許諾を出す場合には、「どの範囲で使われるか」「対価還元はどうするか」「生成物の流通・2次利用をどう管理するか」等、契約条件を明文化しておくことが有効です。
また、生成AI時代における「ブランド価値」「ファンとの関係」「二次創作文化」といった付加価値がサステナブルに守られるよう、ビジネスモデルを見直す機会とも言えます。
- 技術・サービス提供側(AI事業者・プラットフォーマー)視点
許諾取得プロセスを明確にし、データ学習時・出力生成時に「権利クリア」されたものを使うという仕組みを整備することが信頼構築に不可欠です。
学習データの出所・モデルのトレーニングに用いた著作物の種類・量・出処など、透明性を確保することが重要です。
出力結果において、既存キャラクターや著作物と類似/混同されうるものをどう識別・制御するか技術的・契約的なフィルターを強化する必要があります。
また、生成AIを活用しながらも「権利者に還元する」/「共同創作を促す」というビジネスモデルを検討すべきです。
- 制度・政策・市場環境視点
著作権制度はこれまで「人がつくる作品」「人が発信」に基づいて構築されてきたため、生成AIによる“データ学習→生成”という流れに対して制度が追いついていないという指摘があります。
今後、「生成AI利用時のデータ使用許諾義務」「出力の著作類似性判断基準」「権利者還元スキーム」などが議論・制度化される可能性があります。
日本は文化資産(アニメ・マンガ)を重視しており、政府もAI時代における知財政策の先導を目指しており、今回のような強い要請をしています。
企業やクリエイターがこの制度変化・競争環境を見据えて、早めに対応することが競争優位にもつながるでしょう。
文化資産とデジタル革新の両立に向けて
今回のニュースは、単に「AIが勝手にキャラクターを使った」という事件にとどまらず、以下のようなより根本的な問いを投げかけています。
- 文化的価値・ブランド・創作者の努力によって築かれたコンテンツを、生成AIという技術革新がどう扱うべきか。
- 技術の進展を歓迎しつつも、既存の著作権制度・クリエイタービジネスモデル・文化産業構造が置き去りにされないためにはどうすべきか。
- 生成AIを使ったコンテンツ創造の民主化・多様化という期待と、クリエイターの権利保護・適正報酬という責任とのバランスはどうとるか。
この「技術革新 × 文化資産保護」の両立こそが、今後の日本のコンテンツ産業/AI産業双方にとって重大な試金石になるでしょう。私たちも、クリエイター/ビジネス/技術利用者の立場から、それぞれ「どこに立つのか」「何を守るのか」「どう協調するのか」を改めて整理する必要があります。