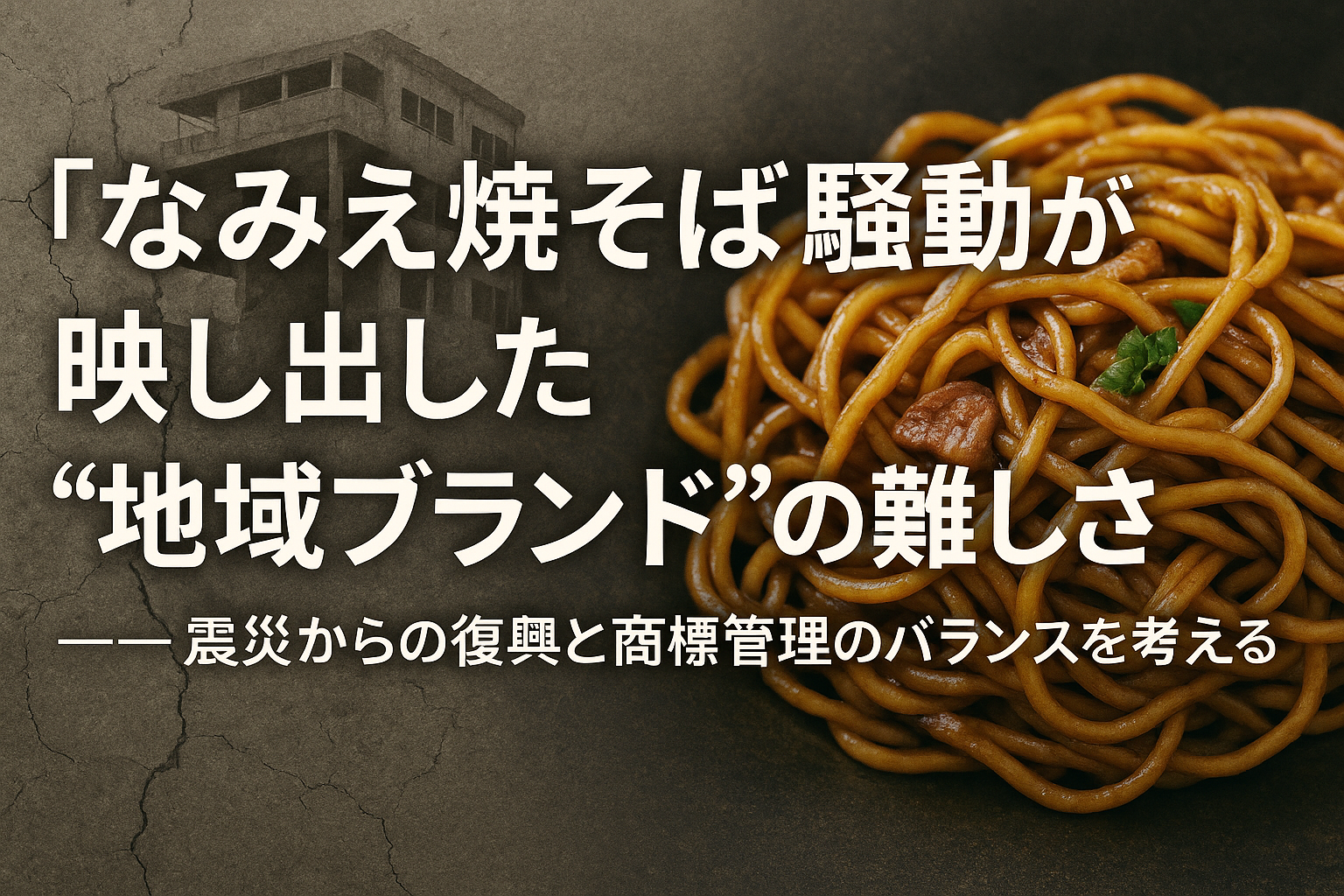福島県浪江町のご当地グルメ「なみえ焼そば」をめぐる商標管理問題が、SNSを中心に大きな議論を呼んでいます。
背景には、震災からの復興の象徴でもある地域ブランドをどう守り、どう育てるのかという、簡単ではないテーマが横たわっています。
本記事では、この騒動を通じて見えてくる地域ブランドの課題や、今後のあるべき方向性について考察します。
「なみえ焼そば」はどう守られてきたのか
浪江町の町おこしの象徴とも言える「なみえ焼そば」は、B-1グランプリをきっかけに全国的に知られる存在になりました。
2017年には、浪江町商工会が地域団体商標として登録し、品質とブランドの維持を図ってきました。
地域団体商標は、地域名+商品名という性質上、全国的な知名度が必ずしも必要ではなく、地域性や一定の知名度があれば登録できます。
この制度は地域振興にとって重要ですが、今回のように商標の管理方法が変化すると、地域内で摩擦が生まれやすいという側面もあります。
騒動の発端は「老舗からのロイヤリティー徴収」
2024年4月から、商標管理が委託会社による運用へ移行し、10月からは提供店に対して
- 登録料:1社3000円
- ロイヤリティー:売上の2.5%
が求められるようになりました。
これに反発したのが、「なみえ焼そば」を震災前から提供してきた老舗「杉乃家」です。
浪江町から避難して営業を続けていた同店のもとに突然「ロイヤリティー徴収の案内」が届き、応じない代わりにメニュー名を「杉乃家の焼そば」へ変更しました。
この話がSNSで拡散され、「昔から提供していた店にもロイヤリティー?」「避難した店への配慮がなさすぎる」などの批判が噴出しました。
法律的には、出願前から正当な目的で名称を使っていた事業者には「先使用権」が認められます。
しかし今回は、制度上の問題ではなく、地域コミュニティの感情的な問題が大きかったと言えます。
商工会側の事情:「ブランド維持にはお金がかかる」
商工会はコメントの中で、普及活動の裏側にある“資金の苦労”を率直に明かしています。
- イベント出店
- 「焼そばマップ」の作成
- 「焼そばサミット」開催
- 小学校での食育活動
こうした取り組みは、浪江町の復興と地域ブランドの育成に確実に寄与してきました。
しかし、補助金・協賛金・クラウドファンディングなどで賄う運営は年々厳しくなっていたようです。
そのため、持続的運営のためには「協賛金」という形で広く負担を求めざるを得なかった、というのが商工会の説明です。
すれ違ったのは「制度」と「心情」
今回の騒動から浮かび上がるのは、制度としての商標管理と震災を経験した地域の心情この二つの齟齬です。
- 商工会側
ブランドを維持するための仕組みを整えたい
- 提供店側
復興の中で長年続けてきた思いがある
突然の費用負担は納得しにくい
特に「杉乃家」は、避難先で浪江町の味を守り続けてきた店です。
町のために続けてきたのに、急に費用を求められれば、違和感を覚えるのは当然でしょう。
このように、“法的には正しいが、心情的には受け入れがたい”という形で対立が生じたのが今回の本質だと考えます。
商工会が謝罪し収束へ。しかし残った「溝」
商工会は杉乃家へ謝罪し、名称の使用も改めて認めました。
しかし同店は「杉乃家の焼そば」として続けることを選びました。
ブランド名をあえて戻さなかった背景には、
- 今回の騒動で感じた不信感
- 商標名に依存せず、店の看板で勝負したいという決意
があるように感じられます。
一度生まれた溝を埋めることは簡単ではありません。
それでも、商工会は説明資料の公開を進め、透明性を高めようとしています。
ここから信頼の再構築ができるかが大きな課題です。
地域ブランドが抱える共通のジレンマ
今回の問題は、「なみえ焼そば」だけの話ではありません。
全国各地で、地域ブランドが力を持つほど、次のような課題が顕在化します。
- 誰がブランドを管理するべきか
- 費用負担の公平性をどう保つか
- 伝統的な提供者をどう扱うか
- 品質維持と自由な活用のバランス
- 復興・地域活性の文脈をどう組み込むか
地域ブランドは、行政・商工会・事業者・住民が作り上げてきた“共有財産”です。
だからこそ、運用ルールの変更には丁寧な対話が不可欠です。
「復興のシンボル」としての未来はどうなるか
震災前に2万人いた浪江町の人口は、現在約2400人にまで減少しました。
町の中心街であった新町商店街も閉鎖が決まりました。
こうした厳しい現実の中で、「なみえ焼そば」には今なお“浪江を思い出す味”“復興の象徴”としての役割が期待されています。
今回の騒動を転機に、
- 地域事業者が誇りを持って提供できる仕組み
- 商工会と事業者が同じビジョンを共有できる体制
- 外部から応援する人たちが関われる柔軟なルール
こうした再設計ができれば、「なみえ焼そば」は再び地域の団結のシンボルとして輝けるはずです。
おわりに:ブランドは“制度”だけで守れない
地域ブランドの強さは、法制度ではなく、作り手・売り手・食べる人この三者の信頼関係で決まります。
今回の騒動は痛みを伴いましたが、そのぶん、地域ブランドの本質を見つめ直す機会になったとも言えます。
「なみえ焼そば」がこれからも浪江町の誇りであり続けるためには、制度の見直しと同時に、心の通うコミュニケーションが求められるのではないでしょうか。
浪江町の次の一歩に注目していきたいと思います。