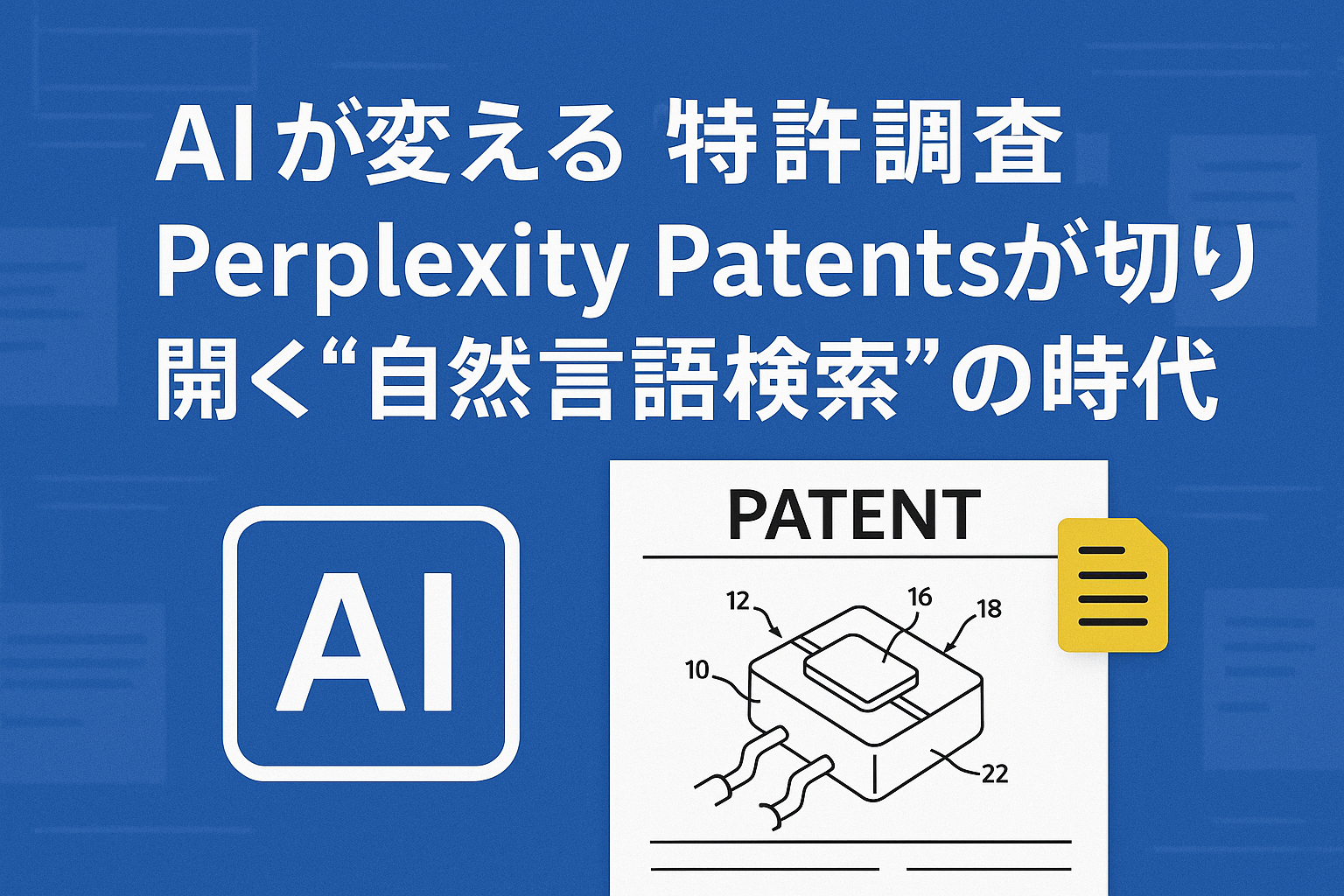生成系AIがとうとう「特許検索」に本格的に踏み込んできました。Perplexityが10月30日に公開した「Perplexity Patents」は、自然言語で「2024年以降の量子コンピューティングの主要特許は?」「言語学習用AIって特許になってる?」のように聞くだけで関連する特許を並べ、元公報へのリンクまで返してくれるというサービスです。しかもベータのあいだは無料で、Pro/Maxなら回数やオプションが増える――これは確かに「誰でも特許にアクセスできる世界」を掲げたくなる出来です。
以下では、このニュースを日本の発明者・社内知財・特許事務所という3つの視点でかみ砕いてみます。
何が“新しい”のか
いままでもGoogle PatentsやJ-PlatPatやEspacenetを組み合わせれば、かなりのことはできました。けれど、どれも「検索式を自分で設計する」のが前提で、FI/FタームやCPCをだいたい分かっていて、キーワードの揺れ(AI / artificial intelligence / machine learning / deep learning…)も自分で面倒を見る必要があった。ここに「自然言語で聞いたらAIがいい感じに拡げてくれる」というレイヤーを一枚かぶせたのがPerplexity Patentsの一番分かりやすい価値です。フィットネストラッカーで聞いたら、スマートバンドやヘルスケア向けウェアラブルまで隣接するものを見せてくる、というあの挙動ですね。
さらに面白いのが、先行技術を特許公報だけに閉じないところです。Perplexityはもともとウェブや論文、コード、公開リポジトリをまとめて答えるのが強みで、それをそのまま「特許のノンパテ文献(NPL)側」に持ち込んでいる。ブログ・動画・OSSからも先行例を拾いにいくと彼らは書いていますが、これは「特許にするか迷ってたけど公開だけはしてた」というグレーゾーンを拾いやすくする方向性で、日本の実務的にはかなり刺さる人が多いはずです。
でも“これだけで先行文献調査が完璧になる”とは言えない理由
とはいえ、実務で怖いのは「網羅性」と「説明責任」です。
- カバレッジの透明性
現時点の説明だと、グローバルに特許をなめるナレッジインデックスを持っていると言っているものの、どの局所公報までどれくらいラグなく入ってくるかははっきりしていません。米・欧・PCTは比較的入りやすいとしても、日本公報(特に公開→特許の追随)や中国公報をどの頻度で反映しているかは、企業のFTO調査ではクリティカルです。ここがブラックボックスのままだと「AIに聞いたらなかったです」はレポートになりません。
- 検索意図の可視化
自然言語で聞けるのは楽ですが、AIが実際にはどのIPC/CPC・どのキーワードを立てて検索しているのかが分からないと、抜けモレの検証ができない。従来の調査報告書が「このFターム群を用い、以下のキーワードで追加検索し…」と書くのは、後続の審査対応や係争で「本当に探したか?」を説明するためです。AIのクエリ生成もこの“証跡化”まで降りてこないと、法律仕事のど真ん中には置けません。
- ハルシネーションとNPLの信頼度
Perplexityはリンクを出すスタイルなのでChatGPTのように“出典不明のそれっぽい公報”をでっちあげるリスクは相対的に低いですが、NPL側での取りこぼしや、逆にノイズを拾いすぎる可能性は残ります。そこを最後に整えてくれるのは結局人間の調査者です。
日本の発明者・研究者にとっての効きどころ
むしろ一番効くのは「出願前の荒い当たり付け」です。アイデア段階で「この分野、米国ではもう山ほど出てる?」を30秒で確認できるなら、社内の発明届出書を書くときに“差別化ポイント”を書きやすくなる。いままでなら特許室に「ちょっと調べてください」と投げていた初動が、自分でできるようになる。これは単純に出願の質を上げるし、無駄な出願を減らす方向にも働きます。
あと、日本語であいまいに聞けるのは地味に大きいです。J-PlatPatをいきなり触るときの一番のハードルは「最初の1語をどう入れるか」なので、そこをAIが吸収してくれるだけでも入口のユーザー層は広がるはず。日本でもすでに「自然言語で特許を検索できるのか」「被引用回数まで見られるのか」を試している人が出てきているので、実務者界隈でもしばらく触ってみる流れはできるでしょう。
特許事務所・企業知財が取るといいポジション
ここはたぶん「置き換え」ではなく「前段の民主化」と捉えるのが一番安全です。つまり、
- 発明者・研究部門にはPerplexity Patentsを触ってもらう
- そこで出てきた“気になる公報”や“似てるNPL”だけを知財部が正式ルートで再検索・再評価する
- そのときに「AIがどういう観点で拾ってきたのか」を説明可能にするためのガイドラインを作る
という3段階で考える。いきなり「これでFTOやろう」「無効資料探そう」とするより、先に「発明届出の質をそろえる」「競合の出願トレンドをざっくり把握する」ところに当てる方が、現実的にリスクが小さいです。
逆に言うと、事務所側はここを“教育コンテンツ”にできます。たとえば「Perplexity Patentsでここまでは見えるけど、実務ではここまで落とし込みます」という比較記事・セミナーを出すと、顧客に対して「AI時代でも弁理士の仕事はここにある」と示しやすい。今回のリリースはまさに「顧客が自分で荒く検索できるようになる」転機なので、事務所は能動的にレイヤーを明示しておいた方がいいでしょう。
今後ありそうな展開
Perplexityは同じ文脈で学術向けの「Scholar」もほのめかしています。研究論文と特許を一続きに見られるようになると、「この手法は論文では先に出てるけど、特許は空いてる」「逆に特許が先んじてるから論文で書くと危ない」といったクロスチェックが一段楽になります。これが実装されると、企業のR&D・知財連携がよりリアルタイムになるので、日本の組織でも「発明届をAIで下書きして、同時に類似特許を引っ張る」というワークフローを2026年あたりに真面目に設計するところが出てくるはずです。
まとめると、Perplexity Patentsは「特許検索を一部の専門家に閉じておく時代」を少し壊す道具です。ただし、壊すのは“入口”だけで、出口――すなわち網羅性の担保、証跡の出力、クレーム解釈、無効理由の構成――はまだ人間と既存DBの領域にあります。なので、今やるべきことは「入口が軽くなった世界で、うちの発明創出や社内説明はどう変えるか」を考えること。AIが特許を探してくれるようになったからといって、あなたが書くべき技術的特徴や実施形態が減るわけではありません。むしろAIが“似てる先行例”をたくさん出してくる分だけ、あなたの明細書はよりクリアで、より差別化されたものである必要が出てきます。そこにこそ、実務者の腕の見せどころがあります。