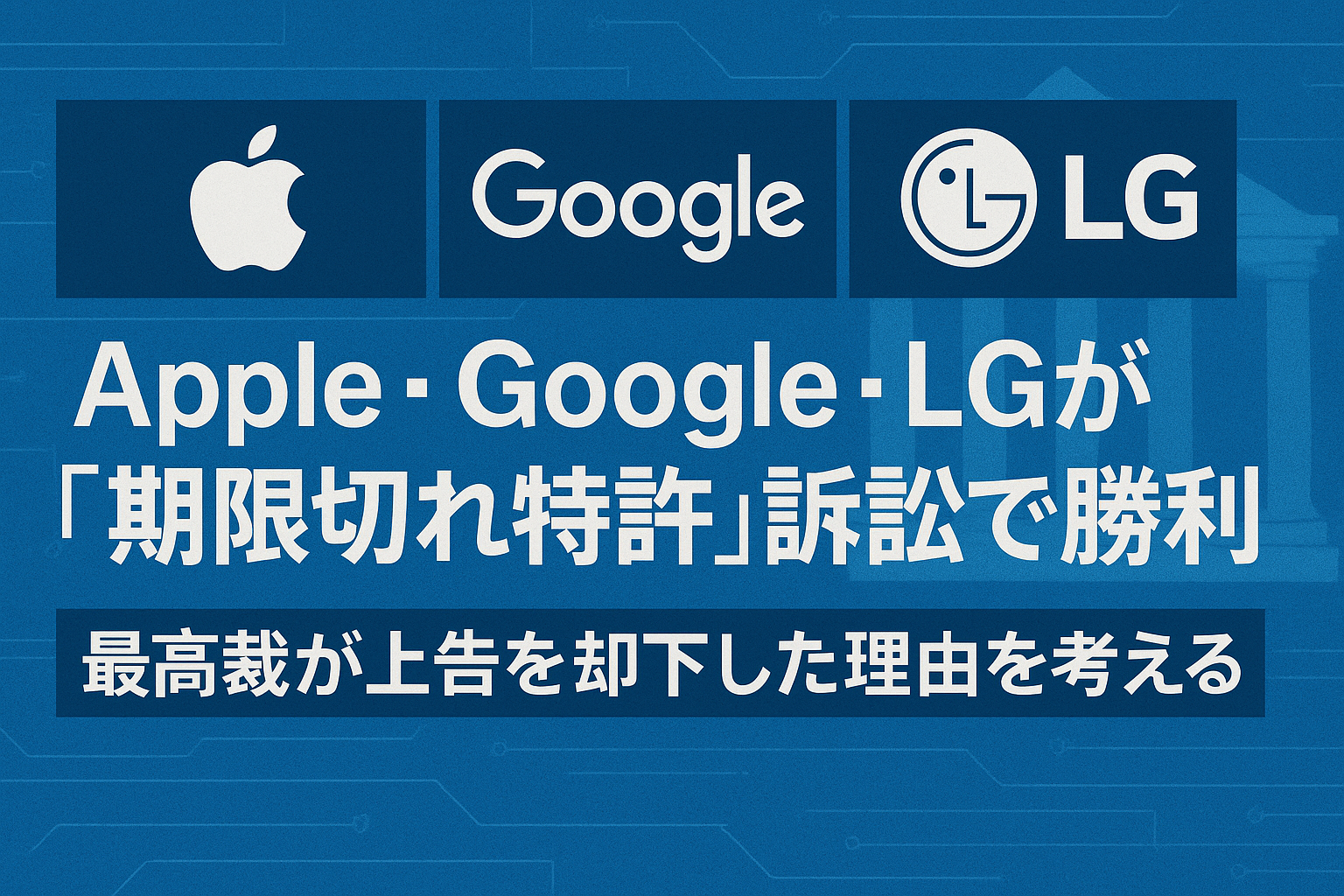2025年、モーションセンサーやカメラ関連の特許を巡る訴訟で、Apple・Google・LGが最終的な法的勝利を収めました。特許はすでに期限切れでしたが、その「扱い」が大きな争点となり、最高裁まで議論が持ち上がった珍しい事例です。本記事では、この訴訟の概要と、その背景にある特許制度のポイントを整理して考察します。
争点となったのは「期限切れ特許の扱い」
Gesture Technologiesは、エンジニアのティモシー・プライヤー氏が創業した企業で、モーションセンサーやカメラ関連の技術に関する複数の特許を保有していました。今回の争いは、そのうちの33件の特許をめぐるものです。
問題の特許は2020年に期限が切れましたが、Gesture Technologiesは「期限切れ前の2020年にApple・Google・LGが侵害した」として2021年に訴訟を開始しました。
これに対し、Apple・Google・LGは特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)に対して特許無効化を申し立てました。結果として、PTABは33件中31件を無効と判断し、さらに連邦巡回区控訴裁判所も「33件すべて無効」と判決しました。
Gesture Technologiesはこれを不服として最高裁へ上告しましたが、ここで争点が大きく変わります。
「期限切れの特許は誰が審査すべきか」という制度上の問題
Gesture Technologiesの主張は、「期限切れの特許は、もはや公衆の権利に関わらないため、PTABではなく連邦裁判所でのみ審査されるべき」というものです。
一方でApple・Google・LG、そしてUSPTOは、「たとえ期限切れでも、過去の権利行使を巡る争いがある以上、公衆の権利に関わる」と反論し、PTABによる無効化判断が妥当だと主張しました。
これは、単なる特許の有効・無効といった技術的議論ではなく、「特許制度の構造」の話です。特許が期限切れになった瞬間、どの機関がそれを判断できるのか――という点を最高裁に問うた形となりました。
最終的に最高裁は上告を却下し、下級審の「特許は無効」という判断を確定させました。
Gesture Technologies側の主張が「通らなかった」理由
最高裁による上告棄却の背景には、いくつかのポイントが考えられます。
- 特許は“期限後”も法的争いの対象となりうる
たとえ期限が切れても、過去の侵害を主張する訴訟が可能である以上、その有効性を議論する必要があります。制度上、PTABは特許の有効性判断という専門的役割を担っており、その判断が「期限切れ特許は扱えない」となる合理性は低いと見なされた可能性があります。
- 技術的にも法的にも「特許の健全性」が求められる
特許制度は独占権を与える代わりに、社会に対して技術内容を公開する仕組みです。だからこそ無効な特許が存続すると市場をゆがめるリスクがあるため、「公衆の権利」に関わると判断されやすい側面があります。
- Gesture Technologiesの主張の説得力不足
Gesture Technologiesは「期限が切れる以前、特許の有効性は疑われていなかった」と述べています。しかし、Apple Insiderは「特許が有効だった期間に侵害訴訟が提起されたことはない」という伝聞情報を掲載しており、特許の強さそのものに疑問符がついたまま争いが進んでいた可能性があります。
大手企業が示した「特許リスク管理」の典型例
今回のApple・Google・LGの動きは、巨大企業が特許リスクにどのように対応するかを示す典型例でもあります。
- PTABの活用
侵害訴訟を起こされると、多くの大手企業はPTABに無効審判(IPR)を申し立て、特許の基盤そのものを揺さぶります。
これは「技術の先行性」や「新規性の欠如」を突く上で非常に効果的です。
- 複数企業の連携
今回はApple・Google・LGがそれぞれ似た立場で動いたため、判例形成の方向性にも影響が出たと考えられます。
- “期限切れ”特許を巡る訴訟の抑止
期限切れ特許であっても過去の侵害を理由に訴訟されることがありますが、今回の判断により、PTABでの無効化が可能であることが改めて示されました。
これは今後、特許主張を検討する小規模企業にとっても大きな参考事例になるでしょう。
今回の判決が示すもの
今回の一連の判断は、特許制度に対する明確なメッセージを含んでいるように見えます。
- 期限切れ特許でも、公衆の権利に影響する場合はPTABでの審理対象となり得る
- 特許を根拠に訴訟を起こす場合、その特許の“強さ”は期限前から厳しく問われる
- 技術企業はリスク回避のために制度的な手段(IPR)を積極的に活用するべきだ
Gesture Technologiesのような小規模企業にとっては厳しい結果ですが、制度全体の健全性という観点では大きな意義を持つ判決だと感じます。
まとめ
今回の訴訟は、単なる「大企業 vs 小規模企業」の構図ではなく、特許制度の根幹とも言える「どの機関が特許の有効性を判断できるか」という問題が争われたケースでした。
最高裁の上告棄却により、PTABの判断権限が再確認され、特許制度の運用における一貫性が保たれたと言えます。
今後もIT企業やスタートアップの間で類似の争いが起きる可能性は十分あり、今回の判例はその際の重要な参考材料になるはずです。