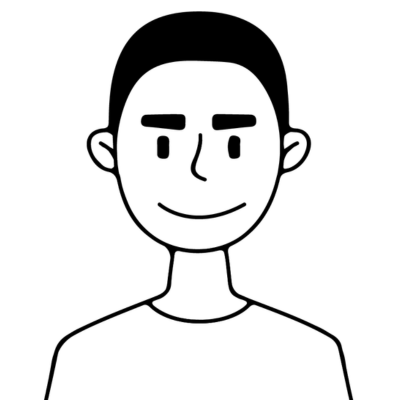FAQ– よくあるご質問 –
-
中小企業関連で申請する場合、出願人が中小企業に該当する者であることを証明するための書類を提出する必要はありますか。
-
出願前に注意すること、何を行えばいいのかを教えてください。
-
意に反して公開されたと考えられる具体例にはどのようなものがありますか?
-
新規性喪失の日から1年以内に第2項の規定の適用を申請し、日本で出願Aを行いました。その後、出願Aを基にPCT出願Bを行い、出願Bを日本に国内移行しました。日本における指定国として、出願Bに新規性喪失の例外規定の適用はありますか?
-
国内優先権を主張する出願を行う場合、先の出願が第2項の規定の適用を受けている際、新規性を喪失した時点から1年以内でなくても、先の出願日から1年以内に特許出願をすれば、発明の新規性喪失の例外規定の適用が可能ですか?
-
セミナーで発明を発表した後、第三者が独自にその同じ発明を発明して特許出願し、その後発表者が特許出願した場合、セミナーでの発表に関して第2項の規定の適用を受けたとしても、発表者の出願は先に出願した第三者によって拒絶されることはありますか?
-
特許を受ける権利を有する者の行為によって公開された複数の発明があり、初めの公開に関する発明には第2項の規定の適用手続きを行わず、初めの発明と同一で、初めの公開行為に密接に関連する後の公開行為によって公開された発明に対しては第2項の適用手続きを行った場合、初めの公開に関する発明に対しても第2項の規定の適用を受けることは可能ですか?
-
特許を受ける権利を有する者が複数の店舗に商品を納品する場合、『証明する書面』にはすべての店舗を記載する必要がありますか?
-
取引先Xに商品Aを販売した後、異なる取引先Yにも商品Aを販売しました。取引先Xへの販売によって公開された発明に関して、第2項の規定に基づく手続を行う予定です。さて、取引先Yへの販売によって公開された発明についても、第2項の規定の適用を受けるためには、別途手続が必要となりますか?
-
X学会で発明Aを発表した後、別のY学会でも発明Aに関する発表を行いました。X学会での発表に関して第2項の規定の適用手続きを行う予定ですが、Y学会での発表についても同様の手続きが必要ですか?
-
論文発表後に学内で図書館による論文の閲覧公開が義務付けられています。論文発表によって公開された発明に対して第2項の規定の適用手続きを行う予定ですが、図書館での閲覧公開についても同様の手続きが必要ですか?
-
セミナーで公開した発明に関して第2項の規定の適用を受けるため、『証明する書面』と共に、セミナーの開催者による証明書を補充資料として提出したいと考えています。セミナーが複数の者によって共催されている場合、共催者全員による証明書が必要ですか?
-
自社のウェブサイトに発明を公開したため、第2項の規定の適用を受けようとしています。公開情報に関する掲載や保全に権限や責任を持つ者による証明書を『証明する書面』の裏付け資料として提出したいのですが、どのような人物の証明書を取得すべきですか?
-
『証明する書面』に記載された事項が事実であることを裏付ける資料として、どのようなものを提出すれば良いですか?
-
公開者の中に、発明の公開の原因となる行為時の特許を受ける権利を有する者以外の他者が含まれている場合、行為時の権利者と公開者の関係が「単なる実験補助者」でない場合、どのような関係が認められるのでしょうか?
-
職務発明の場合で、発明者が従業員であり出願人がその会社である場合も、特許を受ける権利の承継の事実を『証明する書面』に記載する必要がありますか?
-
発明者自身が発明を公開し、その後出願を行いましたが、姓が変わっている場合に問題はありますか?
-
新規性喪失の例外規定の適用を受ける予定で、願書の特記事項にその旨を記載しましたが、後に発明が出願時にまだ公開されていなかったことが分かりました。この特記事項の記載を削除することは可能でしょうか?また、記載が削除できない場合、不利益は生じますか?
-
ある発明について特許出願を考慮していましたが、発明を公開した刊行物の奥付に記載されている発行日から1年が経過してしまいました。しかし、発行所に確認したところ、実際の発行日は奥付に記載された日よりも後だったそうです。現在、その実際の発行日からは1年以内ですが、新規性喪失の例外規定の適用を受けられますか?
-
外国特許庁に提出した対比説明をそのまま原文で対比説明として使用することはできますか。
-
国際予備審査報告書や国際調査報告書に記載された文献を先行技術として使用する場合、その報告書自体を提出する必要がありますか。
-
国際予備審査報告書の結果を先行技術文献と対比説明に使用できますか?
-
特許請求の範囲と明細書を補正してから早期審査に関する事情説明書を提出する方法と、補正案を早期審査に関する事情説明書に記載してから補正する方法、どちらがより良い方法でしょうか。
-
申請と同時に手続補正書を提出する予定で、事情説明書の先行技術との対比欄に補正案を記載する必要があるかどうか。
-
手続補正書を提出予定で、先行技術との対比説明欄に補正案を記載すべきか、そしてその記載の位置づけについての指針は何ですか。
-
補正案を提出する際、早期審査の申請と同時に手続補正書を提出する必要がありますか?
-
対比説明は数百ページになる可能性があるが、何ページ以内に収めるべきか。
-
中小企業の出願において、先行技術の開示があるが、対比説明が不十分な場合、事情説明書で同じ文献を引用して対比説明しても問題ないかどうか。
-
先行技術を見つけたが十分な情報が得られない場合、対比説明を省略できるでしょうか。
-
分割出願を行う際、元の出願に対する拒絶理由通知書に記載された文献なども申請に記載した方が良いですか。
-
先行技術調査で外国の重要な関連文献が見つかった場合、それに関して対比説明を提供したほうが良いでしょうか?
-
明細書で先行技術を開示している場合、記載方法についてどうすべきでしょうか?